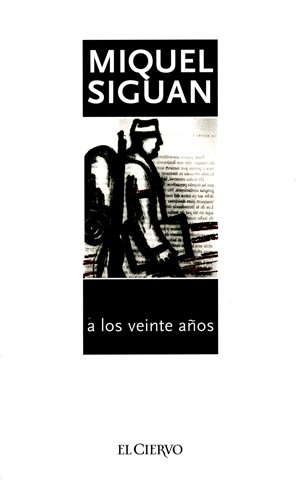―「歴史の記憶に関する法律」(La Ley de la Memoria Histórica) ―
(法律第52/2007号)
2007年12月26日に「歴史の記憶に関する法律」がスペインの国会で成立し公布されました。この法律のおもな狙いは、1936年の内戦開始から1975年のフランコ総統の死で独裁政治が終わるまでの40年間に、政治的な理由で不法に投獄されたり処刑されたり、あるいは亡命して外地で一生を終わった人たちを含めて、何十万人にも及ぶと見られるフランコ独裁政権の犠牲者たちの名誉回復を図ろうとするものです。また内戦中に左翼過激派に暗殺された聖職者たちも、この対象に含まれています。
この法律の骨子は、国として上に述べたような人権侵害があった事実を認め、犠牲者の名誉回復のため種々の処置をとること、具体的には、生存者に対する一時補償金の支給、共同墓地に埋葬された遺体の捜索・鑑定への協力、クーデターや独裁政治を賞揚する記念碑その他の撤去、フランコが建てた「戦没者の谷」と称するマドリッド近郊の戦没者記念施設の見直し、内戦及び独裁制に関する歴史資料の保存、亡命者の子孫に対するスペイン国籍の付与、一連のフランコ時代の治安関係法の廃止、などが謳われています。
すでに内戦から70年を経て、生存者がごく少くなっている現状を考えると、経済面での補償措置には実質的な意義はあまりないのでしょうが、犠牲者の家族にとっては、多分に象徴的な色彩が濃いとはいえ、不当な投獄・処刑が行われた事実を国が正式に認め、何らかの救済措置に踏み込んだことは朗報と言えます。
(封印されていた内戦の記憶)
私は1970年代に、フランコ将軍の死を間にはさんで足掛け10年近くをスペインで暮らしました。75年の11月に病床のフランコの死が近いことをラジオで聞いた近所の老人が、「少しは缶詰を買いだめしておかなくちゃ」と呟いていたのが印象に残っています。
あの頃は、内戦を身を以って体験した多くの人たちがまだ健在で、左右の政治勢力の激突がフランコ将軍のクーデターを生み、それがお互いに顔見知りの間ですら憎しみ殺しあうような悲惨な内戦にまで発展した記憶は、スペイン人の心の奥に傷のような形で残っていました。そして「軍人たちがまたクーデターでも起こすんじゃないか」というのは、当時の多くの市民の頭の片隅に常にあった懸念でした。
そして70年代と言えば、だいぶ緩和されたとは言えまだ言論統制があり、政府に都合のいい話しかおおやけには知らされない仕組みでしたので、内戦中にフランコ軍の占領地域で、共和派支持者とみなされた市民に対する暴行や大量虐殺があったことや、内戦終結の後も20万人を越える政治犯が獄中にいて、少なからぬ政治犯の処刑が内戦後も続いたことなどは、うわさ話として耳にすることはあっても、本当に何が起こったのか外国人にはその全貌がなかなか掴み難い時代でした。
そして地元の人たちから内戦についてくわしい話を聞く機会も多くはありませんでした。当時のスペイン人の大半は、余りにも痛ましい身内の戦争について思い出すことも語ることも気が重くて、いわば戦争の記憶に封印をして暮らしていた、というのが実態だったと思います。
(なぜいまスペイン内戦なのか)
「歴史の記憶に関する法律」が内戦から70年を過ぎたいまになって成立した背景には、もう武器をとって戦争に参加した世代が90歳を越えるようになり、生き証人の数も少なくなって来たことで、スペイン人の内戦に関する記憶の封印もすっかり解け、冷静に過去を振り返る心の余裕が生まれて来た、という事情があると思います。
そして、フランコ独裁政治の犠牲者の名誉を回復することは、民主主義国家として果たすべき義務である、と言う社会主義労働者党内閣の考え方が大多数の国民に受け入れられた、ということでしょう。
しかし議会最大野党の国民党が法案に反対したことを見ても、必ずしも全国民が諸手を挙げて賛成しているとは思えないので、実際に地方自治体に判断が任される部分、たとえば独裁時代の名残を留めるシンボルマークの撤去などが、どこまで実行されるのか不明な部分があります。
またこの法律に勢いを得て、内戦または独裁政治による被害の補償を求めて、国を訴訟する動きが起こるのではないかという見方もあり、スペイン人にとってまだまだ内戦は完全に終わってはいない、という気がします。
(内戦に題材をとった映画)
このところ内戦をテーマにした映画の新作が毎年紹介されていますが、最近バルセロナで「13本のバラ」と「空を見上げて」という2本の映画を見る機会がありました。「13本のバラ」は内戦が終わった1939年の8月に、統一社会主義青年連盟(共産党系)の活動家とその友人たち合計13人の若い女性たちが、非合法の反政府運動に関わったというだけの理由で、マドリッドで銃殺刑にされた実話に基づく作品です。後半からメロドラマ調になってしまったのはちょっと残念でしたが、当時のマドリッドの緊迫した雰囲気の描写が目を引きました。
「空を見上げて」は、1938年3月のイタリー空軍機によるバルセロナ爆撃をテーマにした作品でした。バルセロナの空爆は3日間に亙り、2千人を越える被害者が出ています。その後の第二次大戦の被害に比べれば大したことはないような感じを受けますが、「非戦闘員を目標にした大都市の空爆」という、いわばそれまでの禁じ手をファシスト軍が使い始めたという意味で、歴史に残る出来事でした。
どちらも映画としての仕上がりは今ひとつという感じですが、バルセロナ市の空爆70周年ということもあり、いずれも暗いテーマにしてはずいぶん話題になった作品でした。
それと、完成はまだ2-3年先ということになっていますが、「オール・アバウト・マイ・マザー」で1999年のオスカー賞をとったペドロ・アルモドバル監督が、パブロ・ネルーダの友人で獄中詩人として名を知られるマルコス・アナの回想録(本名フェルナンド・マカロ。共産党員として内戦に参加、捕虜となり死刑の判決を受けるが、22年を獄中で過ごした後、1961年に釈放)の映画化を構想中、というニュースが今年2月に大々的に報道されました。
アルモドバルの新聞談話によると、この詩人の生涯に惹かれる理由のひとつとして、「フランコから非人道的な扱いを受けたことを、決して忘れはしないが復讐は求めない、という考え方で、しかも内戦の犠牲者が国民和解の妨げになってはならない、という態度を貫いているのに感銘を覚えた」と言っています。
マルコス・アナは19歳から41歳までの22年間を、仲間を救うため拷問に耐え黙秘を守り通して独房で過ごしました。その間に頭に浮かぶ詩を手製のインクで皿の裏に書き付けたりして詩作を続けたそうです。自分を警察に密告した友人の名前が判明しても、それには触れず「いま一番大事なことは、スペイン人が身を以って体験した内戦と、それに続く惨禍を二度と繰り返してはならない、ということだ」と物静かに語る88歳の詩人に、アルモドバルは「最近は何かと言えばすぐ犠牲者が町に出て、甲高く自らの痛みを訴える傾向にある中で、マルコス・アナは内戦犠牲者のあるべき姿を我々に示している」と語っています。
スペイン内戦の歴史を辿っていると、外国人の私ですら、ときおり残り少ない髪の毛が逆立つような思いにかられることがあります。戦争中もそして戦後も、一貫して「和解」は問題外とはねつけ、ファシズムに反対する勢力を徹底して殲滅することしか眼中になかったフランコ独裁政治のあり方を思うとき、「それでも復讐は求めるべきでない。内戦の犠牲者が国民和解の妨げになってはならないのだ」と主張するこの内戦の生き証人の言葉が、ずっしりと重みをもって響く由縁です。そしてその言葉は、きっとスペイン内戦だけに限らない真理を含んでいるのだと思います。