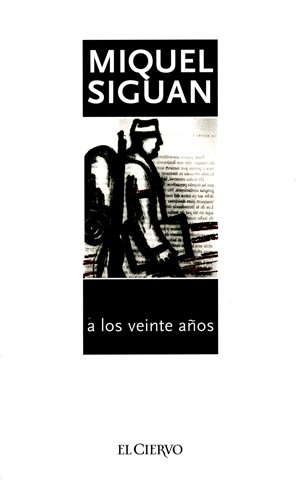.jpg) クリックして地図を拡大
クリックして地図を拡大
クリックして地図を拡大
 クリックして画像拡大
クリックして画像拡大アンドレ・マルローとスペイン内戦
アンドレ・マルロー(André Malraux 1901-1976)は、1936年7月にスペイン内戦が始まったとき、共和国政府支援のためいち早く国際航空隊を組織し、内戦の渦中に身を投じた人です。そして航空機に関しては全くの素人ながら、将来の戦争で空軍の果たす重要な役割を予見していた人でした。1936年8月に発足し、のちに ‘’スペイン飛行中隊(Escuadrilla España)‘’ と呼ばれる国際航空隊は、フランス製の爆撃機Potez-540のほか旧式の護衛戦闘機などをあわせ30機前後を保有する部隊でした。マルロー自身もときおり爆撃機に乗り込み、実戦に参加しています。
約半年間を戦場で過ごしたあと、マルローは1937年2月に国際航空隊が共和国空軍に編入されたのを契機に、戦場を離れ北米での講演旅行など文筆面で共和国支援の活動を続けます。そして、スペイン内戦の経験をもとに執筆した小説『希望』を1937年末に出版したのに続き、1938年の夏からはその映画版『希望―テルエルの山々』(L’Espoir - Sierra de Teruel)の制作に没頭しました。なお小説『希望』の日本語訳は、新潮文庫(岩崎力訳、上下二冊)から1971年に出ています。
.jpg) Potez-540 bomber
Potez-540 bomberスペイン飛行中隊(Escuadrilla España)
映画『希望 - テルエルの山々』は、小説『希望』第三篇の後半でテルエルの爆撃行を扱っている部分を、脚本として再構成したものです。映画のあらすじは、1937年2月半ばのある明け方、スペイン飛行中隊の三機のPotez-540がバレンシア近郊の共和国軍飛行場を発進し、テルエル市北方のフランコ軍秘密飛行場の爆撃に向かいます。基地のありかを通報した農民を案内人として指揮官機に同乗させ、フランコ軍の秘密飛行基地を上空から発見し徹底的に爆破しました。(映画では、続けて近くにある重点目標の橋の爆破にも成功することになっています)。
隠密爆撃は大成功でした。しかしその帰途、フランコ軍の別の基地から飛び立ったHeinkel 51戦闘機の攻撃に遭い、一機のPotez-540がテルエル市北東のバルデリナレス村(Valdelinares)近くの山中に墜落してしまいます。
生存者がいるとの通報に、バレンシア基地から指揮官のマニャン(Magnin)が大急ぎで車で救助に駆けつけました。しかし車で行けるのはリナレス・デ・モラ村(Linares de Mora)まで。墜落現場に近い標高1600米を越えるバルデリナレス村までの10キロの急な山道を、歩いたりロバの背に揺られたりして片道三時間をかけて登り、地元の人たちの協力を得てぶじに負傷者を救出し遺体を収容する、という物語です。
秘密飛行場を超低空飛行で探しあて、爆撃に成功するまでの緊迫感、Heinkel 51戦闘機との息を呑む空中戦の場面など、小説も映画もどちらも実戦を経験したマルローならではの描写が際立っています。なおこの『希望』に登場するテルエル空爆の話は1936年の話で、その一年後の1937年12月から1938年2月にかけてのテルエル市攻防をめぐる激戦、いわゆる「テルエルの戦い」とは別物です。
 View of Linares de Mora
View of Linares de MoraLinares de Mora
リナレス・デ・モラはテルエル市の北東80キロ足らずの高地にあり標高1300米、いまは立派な舗装道路が通じていて、テルエル市から車で一時間ちょっとの距離です。しかし70年前のリナレスへの道はずいぶん違った雰囲気だったようです。
小説『希望』の中で、バレンシアから車でやってきた航空隊指揮官のマニャンが、ふもとのモラ・デ・ルビエロスの町からリナレスに向かった時の様子を、マルローはこんな風に描写しています。
「やっとマニャンはリナレスに向けて出発した。そこ(モラ・デ・ルビエロスの町)を出た彼は永遠のスペインに入って行ったのだった。(中略)いたるところ段々畑と岩と木だけなのだ。車が斜面をおりるだびごとに、マニャンは飛行機が絶望的にこの地面に近づいていく情景をまざまざと見る思いだった」
(岩崎力訳新潮文庫(下巻))
「永遠のスペインに入って行った」というのは、フランス語の原文に近い日本語訳なのでしょうが、英語版では‘’At last, Magnin left for Linares. From now on, he was in touch with the very soul of Spain’’(S. Gilbert & A. Macdonald訳)となっています。
この部分は、「まるで中世の昔から時間が止まっているような、いかにもスペインらしい世界に足を踏み入れた」、という意味ではないかと思います。
 Linares de Mora(view from the town)
Linares de Mora(view from the town)映画『希望 - テルエルの山々』(L’Espoir - Sierra de Teruel)
「リナレスは城壁にかこまれた町である。子供たちが門の両側の城壁によじのぼっていた。」というのが、マニャンの目に映ったリナレス・デ・モラの第一印象でした。
いまは城壁に囲まれた町というよりはもっと開けた雰囲気ですが、リナレスは典型的な過疎地帯で、内戦当時は人口千人くらいの比較的大きな村でしたが、いまでは住民は300人前後にまで減っています。
スペイン共和国政府がなけなしの財布をはたいて拠出した資金援助をもとに、映画『希望 - テルエルの山々』の撮影は、1938年8月からバルセローナ市のモンジュイックの丘にあるスタジオを使って始まりました。バルセローナでは年初いらいフランコ軍とイタリア軍による空爆が激しくなり、停電がひんぱんに起きフィルムの現像にも支障を来たす状態で、ネガは全てフランスに送りパリのパテ社で現像したそうです。
リナレス一帯はすでにフランコ軍の支配地域だったので、墜落機の乗組員を救助する野外シーンは、バルセローナ近郊のモンセラット山で2500人のエキストラを動員してロケをしています。
マルローは、バルセローナ市がフランコ軍の手に落ちる直前まで踏み止まり撮影を続けましたが、1939年1月下旬に撮影機材一式を車に積みこみ、多くのスペイン人亡命者であふれかえっているフランス国境を越えます。撮り残した分はフランスで仕上げ、音楽はダリウス・ミヨーが担当し、映画は1939年6月に完成しました。
内々の試写会では大好評で、1939年8月に一般公開を予定していましたが、フランス政府の検閲に引っかかり陽の目をみませんでした。結局公開されたのは戦後の1945年のことで、その年のルイ・ド・リュック映画賞を受けています。
検閲で公開禁止の決定が出た背景には、フランコ政権の意向を汲んだ当時の駐スペイン大使ぺタン将軍が、ダラデイエ内閣に働きかけたためと言われます。そして1940年6月にフランスを占領したナチスの手で、『希望』のオリジナル・ネガフイルムは廃棄処分されましたが、コピー済みのポジフィルムが別の場所に保管されていたため、全損の難を逃れました。
私の手元にあるのは、2003年にポジフィルムから起こしたフランス製のDVD(スペイン語版)ですが、『テルエルの山々』はまるでサイレント映画でも見るような力強い映像が印象的です。私はこの記事を書くため改めて見ましたが、繰り返し見ても十分鑑賞に堪える作品です。劣悪な環境でよくこれだけの内容の作品を作り上げたものと感心します。
マルローが「テルエルの戦いの同志たちに」と副題をつけた小説『希望』を書いた1937年は、まだスペイン共和国政府の勝利に希望を持てる時期だったのかも知れません。しかしその映画化に取り組んだ1938年後半は、もう内戦が共和国の敗北に終るのは目に見えているという情勢でした。しかしマルローは『希望』の撮影に没頭します。
映画は、山の斜面を埋め尽くすほどのおおぜいの村人たちが、右の拳を高く挙げ連帯の挨拶を送るなか、担架に担がれた負傷者とロバの背にくくりつけた棺を守る人たちの長い長い列が、静かに山道をおりてくる場面で終ります。「もう何も手伝ってもらうことはないので家で休んでくれ」と告げられた老人が、『いや、まだ私にも感謝の気持ちを表すことはできる』と右の拳を高く挙げ、棺を見送る人たちに加わる話は、小説にはなく映画の脚本で付け加えた部分です。
フランコ軍の砲撃がしだいに近づくのを耳にしながらバルセローナに踏み止まり『希望』の撮影を続けたマルローは、たとえスペイン共和国政府に終わりが来ることはあっても、人間の尊厳を踏みにじる勢力との戦いが終わることはない、と固く信じていたのだろうと思います。
そして、まだ死者に対して感謝の気持ちを表すだけのことはできる、と主張する老人の話を脚本につけ加えたり、何千人ものエキストラを動員しダリウス・ミヨーの音楽が響き渡るあの大掛かりな行列の場面を映画の結末としたのは、戦死した全ての同志に対する鎮魂の祈りという面もあるでしょうが、むしろ、ファシズムとの戦いは必ず生き残った者の手で続けられて行く、というマルローの将来への確信を表現したかったのではないでしょうか。マルローはスペイン内戦の次に来るものを予感したからこそ、あえて『希望』という名の映画制作に打ち込んでいたのだろうと思います。
.jpg) Mosqueruela, medieval town on the highland east of Teruel
Mosqueruela, medieval town on the highland east of TeruelMosqueruela
リナレス・デ・モラからさらに15キロぐらい山肌ぞいに曲がりくねった道を走ると、モスケルエラ(Mosqueruela)という変わった名前の町に着きます。標高1470米、人口700人くらいの、中世からの古い歴史を持つ町です。この山岳地帯はかつては牧羊が盛んで、モスケルエラは羊毛の集散地として19世紀まで栄えた町です。しかしこの地方は19世紀後半のカルリスタ戦争と呼ばれる内戦の舞台となり、農民は離散し牧羊は壊滅的な打撃を受けてしまいす。
.jpg) Mosqueruela's city wall
Mosqueruela's city wall中世の町モスケルエラ
この写真はロマネスク建築を思わせる町の城壁の一部です。モスケルエラの町の歴史は13世紀にまで遡ります。モスケルエラから北東に延びる山沿いの道でつながるこのあたりの山岳地帯を、マエストラスゴ地方(Maestrazgo)と呼びますが、中世の名残りを感じさせる、小さな町に出会うことの多い地域です。
 Narrow street of Mosqueruela
Narrow street of Mosqueruela永遠のスペイン
私たちが石畳のせまい道をぶらぶら歩いていたとき、買い物の途中らしい老婦人とすれ違いました。「こんにちは」と挨拶したら、「どちらから?」と尋ねられました。一瞬とまどいましたが、「バルセローナから」と答えたところ、「まあ、そんな遠いところから」と本当に驚いた風でした。この老婦人にとっては、400キロ離れたバルセローナは外国のように感じられたのかも知れません。うっかり「日本から来た」などと口にしなくてよかったな、と思いました。
老婦人は、もし私たちが道を尋ねたら、自分の買い物はさておき一緒に案内してくれそうな人でした。アンダルシアでもこんな地元の人たちに出会いました。時代の流れから取り残されたように見えながら、実は昔からの生活のリズムを大切にすることで心安らかな毎日を送り、外来者に出会えば素直に驚き、そして暖かく接することのできる人たち。そんなスペイン人が、マルローの「永遠のスペイン」に住む人たちではなかったかと思います。