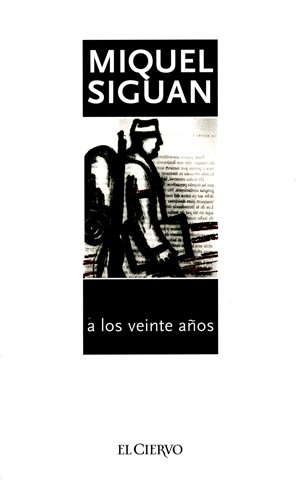Map+a+de+Espa%C3%B1a-San+Juan+de+la+Pe%C3%B1a(PSD)+Sep+16,+2010.jpg) スペイン地図 Map of Spain
スペイン地図 Map of SpainIMG_4461+4x6(800+pix).jpg) (1)修道院への道(The road to San Juan de la Peña)
(1)修道院への道(The road to San Juan de la Peña)(Please see the summary in English at the end of this article)
サンフアン・デ・ラ・ぺーニャ修道院(Monastery of San Juan de la Peña)
前回ご紹介したハカ大聖堂から西に20数キロ、急カーブの続く山道を標高1,100米くらいまで一気に登ると、まるで岩山に彫り込んだような異様なその姿と、回廊の彫刻で有名なサンフアン・デ・ラ・ぺーニャ修道院が、とつぜん右手に現れます。ぺーニャ(peña) は岩とか岩山を指すので、サンフアン・デ・ラ・ぺーニャ修道院は、「岩山の聖ヨハネ修道院」という意味になります。
 (2)修道院(The Monastery)
(2)修道院(The Monastery)サンフアン・デ・ラ・ぺーニャ修道院の歴史と時代背景
この修道院、正確には修道院跡が、どのような事情でそして誰の手でこの岩山に建てられたのか、その起源ははっきりしません。7世紀ころから岩山の洞窟に起居し、瞑想の生活を送る隠修士と呼ばれるごく少数の修道士たちがいた、という伝承はあるものの、修道院として記録に登場するのは10世紀ころの話。有名な修道院ながら、その歴史には謎の部分を含んでいます。
前回にも述べた通り、11世紀の後半にアラゴン王国がサンチョ・ラミレス王(在位1063-1094)のもとで、徐々にイスラム勢力の支配地を侵食し領土拡張の勢いを示し始めたころ、サンフアン・デ・ラ・ぺーニャ修道院はアラゴン王家の霊廟となり、同時にサンティアゴ巡礼路の聖地のひとつとして有名になります。そして王家や貴族からの寄進により拡張工事が進み、11世紀の終わりころには回廊を除き、ほぼ現在の姿に近いロマネスク修道院としての形が整いました。
11世紀後半は、ハカ大聖堂とサンフアン・デ・ラ・ぺーニャ修道院がアラゴン王家の庇護を受け、アラゴン地方での宗教活動の中心として大いに発展した時期です。しかしサンチョ・ラミレス王が1094年7月、自らの将来を賭けたウエスカ攻略戦の最中に戦死したため、長男のペドロ1世がそのあとを継ぎ1096年にイスラム勢力からウエスカを取り戻しますが、12世紀に入るとサンフアン・デ・ラ・ぺーニャ修道院を取り巻く環境はしだいに変わっていきます。地の利を得たウエスカが新しい首都となり、政治や宗教活動の中心がしだいに新しい首都に移って行ったためです。ハカ大聖堂と同じく、サンフアン・デ・ラ・ぺーニャ修道院にも、時代の流れに取り残された歴史があります。
IMG_1614+Parador+3x4(600+pix).jpg) (3)新修道院(現在はホテルと記念館に改装)(New Monastery converted into a hotel)
(3)新修道院(現在はホテルと記念館に改装)(New Monastery converted into a hotel)IMG_1496Camino+al+monasterio+viejo+4x4.2(600).jpg) (4)旧修道院への山道(Mountain road to the Old Monastery)
(4)旧修道院への山道(Mountain road to the Old Monastery)1675年2月に発生した火災は三日三晩続き、修道院の建物が甚大な被害をこうむったため、1キロぐらい離れた場所に新修道院が建てられましたが、2007年にはその新修道院の建物も改装され、パラドールと呼ばれる4星のホテルと、アラゴン王国とロマネスク修道院の記念館になっています。パラドールからは小型バスがサンフアン・デ・ラ・ぺーニャ旧修道院向けに出ていますが、写真のような中世以来の旧道を歩いてもホテルから20分ぐらいの距離です。
IMG_4702+Vista+de+arriba+de+Iglesia-Claustro,+Sa%2B15.jpg) (5)教会と回廊(修道院南面)(South view, Church & Cloister)
(5)教会と回廊(修道院南面)(South view, Church & Cloister)おおざっぱに言えば、手前に見える回廊の床から下の部分が「旧教会」(10世紀の前ロマネスク様式の建築)で、それを土台に「新教会」と呼ばれる11世紀以降のロマネスク建築をその上に継ぎ足した構成になっています。なお回廊部分は12-13世紀の建築とされています。
IMG_4746+Fachada+Dist,+Curve,sa%2B10+3x4.5.jpg)
(6)修道院の西面(West view of the Monastery)
これは同じ修道院を西側から道路ごしに眺めたものですが、左の横長の建物が2階建ての修道士たちの居住区で、内部で「旧教会」につながっています。中央に見える教会の建物は、半円形のガラス窓から上が「新教会」、その下が「旧教会」に当たります。なおこの写真では見えませんが、修道院の入り口は建物の左横についています。
前ロマネスク様式の旧教会(10世紀)
IMG_4608+Iglesia+vieja+4x2.8.jpg) (7)旧教会(Old church, pre-Romanesque style)
(7)旧教会(Old church, pre-Romanesque style)旧教会(前ロマネスク様式)
この写真は1階(実際には半地下)の修道士たちの居住区から、その奥に位置する旧教会の方向を眺めたものです。旧教会は細長い明り取りの窓が二つあるだけの、まるで洞窟を思わせる雰囲気です。なお奥が明かるいのは人口照明によるものです。
この修道士の居住区は11世紀の拡張工事で付け加えられたものですが、ガイドの説明では、この修道院の初期には20人足らずの修道士と修道女が共同生活をしていたが、修道女たちは11世紀末ころにに数キロ離れたサンタ・クルス・デ・ラ・セロスに創建された女子修道院に移った、とのことでした。この1階の居住区もほとんど陽がささず湿気もあり、住む場所としては最悪ですが、こんな環境に耐えるのも修行の内、苦行が宗教体験を深める、というような見方があったのでしょうか。
IMG_4631+Altarles+dobles+2.8x4.3.jpg) (8)二連の祭壇(Twin altars of the old church)
(8)二連の祭壇(Twin altars of the old church) 旧教会はまさしく岩山を削って建てたという感じで、ふつうなら二つの祭壇のうしろが半円形に張り出し、明り取りの窓が付くところですが、むろん窓はなく岩盤がむき出しのままです。
この旧教会のように10世紀の建築は、ロマネスク(11-12世紀)に先立つという意味で、前ロマネスク(Pre-Romanesque)様式と呼ばれますが、祭壇前や教会内部の仕切りに使用されている馬蹄形アーチは、前ロマネスク建築でよく見かけるもので、これが建設時期を判断するひとつの手がかりにもなります。
なお祭壇と教会内部が二つに仕切られているのは、修道士と修道女がそれぞれ別の祭壇を必要としたため、という説があります。
IMG_4624+Pintura+mural.jpg)
(9)壁画(Mural painting)
左祭壇の天井に、12世紀ころの作品と推定される壁画が一部残っています。大半は17世紀の火災で焼け落ちてしまったのでしょう。
貴族たちの霊園
IMG_1566+Patio-Pante%C3%B3n+de+nobles+USM(20),.jpg) (10)貴族の霊園(Pantheon of Nobles)
(10)貴族の霊園(Pantheon of Nobles)IMG_4602++Nichos+del+nobels.jpg) (11)貴族の霊園(Pantheon of Nobles)
(11)貴族の霊園(Pantheon of Nobles) IMG_4601+Crismon+USM(40),+Curve,.jpg) (12)貴族の霊園(Pantheon of Nobles)
(12)貴族の霊園(Pantheon of Nobles)地下の旧教会を出て新教会に向かう途中に中庭があり、その中庭の左手、岩壁に沿ってアラゴン王国の有力貴族たちの霊園が設けられています。棺を収納した扉には各自の紋章が彫りこんであり、彫刻としてもなかなか立派なものがあります。なお王家の墓はこの霊園の後ろ、外から見えない場所に位置しています。なお中庭の正面奥に見えるのが、1094年に完成したロマネスク様式の新教会への入り口です。
新教会(ロマネスク様式-11世紀)
IMG_4482+Vista+hacia+el+altar+central.jpg) (13)新教会(Romanesque church)
(13)新教会(Romanesque church)ロマネスク様式の新教会には三つの祭壇がありますが、地下の旧教会と同じく、いずれも祭壇の奥は岩壁のため窓はありません。写真の明かりは人工照明によるものです。
IMG_4496+Apse+USM(70),.jpg)
(14)中央後陣(Central apse)
IMG_4639+Ceiling++USM(60),.jpg) (15)教会の岩天井(Rock ceiling of the Romanesque church)
(15)教会の岩天井(Rock ceiling of the Romanesque church)祭壇に近い部分は岩天井になっていて、しばらくじっと見つめていると圧迫感を感じるほど、迫力のある天井です。
IMG_4600+Puerta+moz%C3%A1rabe+hacia+claustro.jpg) (16)回廊への扉(Pre-Romanesqsue door to the Cloister)
(16)回廊への扉(Pre-Romanesqsue door to the Cloister)ロマネスク教会の右手の扉は回廊に通じています。この回廊への入り口は優雅なイスラム風の馬蹄アーチを描いており、地下の旧教会と同時期の作、すなわち10世紀ころの前ロマネスク様式の作品というのが通説です。ただし新教会自体は11世紀のロマネスク建築でありながら、なぜこの入り口だけが1世紀前のものなのかというのは、いろいろ議論のあるところです。もともと地下の旧教会にあったものを移転して再利用した、という説に従っておきます。馬蹄形、鍵穴形など呼び名はいろいろありますが、このイスラム風アーチを見ると、年月を経て磨きぬかれた様式が持つ、端整という言葉がふさわしい美しさを感じます。
IMG_4576+Puerta+moz%C3%A1rabe.jpg) (17)馬蹄形アーチ(Horseshoe arch)
(17)馬蹄形アーチ(Horseshoe arch)これは同じ入り口を回廊の側から眺めたものです。アーチは18個の石で構成されていて、写真ではよく見えませんが、その石のひとつひとつに文字や紋様が刻んであります。「この扉は、信ずる者に天国への道を開く」という意味のラテン語文が彫りこんであるそうです。
回廊(Cloister)
IMG_4583+El+Claustro+USM(20),+Curve,+Sa%2B10,+C-20,.jpg) (18)回廊(Cloister)
(18)回廊(Cloister)回廊
教会から一歩足を踏み出すと、吹きさらしの回廊に出ます。ふつう修道院の回廊というのは、四方を壁で囲み、廊下は屋根付きで、中庭には芝生や木々あるいは噴水などを配してあり、修行に疲れた修道士たちの心をなごませるような配慮を感じさせるものですが、この回廊は屋根代わりの岩山が頭上におし迫り、西北からの寒風がもろに吹き付けるというぐあいで、とても心休まるどころではありません。私が訪ねたのは四月初めのことでしたが、身を刺すような冷たい風が吹き、カメラのシャッターを押す手がかじかんで仕方がありませんでした。東方向からは岩山が迫っているため、回廊は西に向かって開いていますが、そのため晴天の日でも日没前の数時間しか陽が当たらないという、なかなか厳しい環境です。
IMG_4539+El+Claustro(resto+de+pared).jpg) (19)回廊(Cloister)
(19)回廊(Cloister)これは回廊の西の端(写真の左手方向)が、もともと壁で遮蔽してあったらしいことをうかがわせる写真です。赤い矢印で示してある部分が、大火の際に崩壊してしまった西壁の一部かと推測されます。
IMG_4536+Un+arco+del+lado+sur3.5x5(600).jpg)
(20)回廊(Cloister)
これは回廊の南側から教会を眺めた写真ですが、アーチ部分の装飾にハカ大聖堂でおなじみの、「ハカのサイコロ紋様」と呼ばれる切り餅を並べたような紋様が見られます。この回廊は12-13世紀の建築で、ハカ大聖堂よりだいぶ後のものですが, ハカ紋様がいかに広範にアラゴン一帯に広がっていたかを物語っています。
柱頭彫刻
この修道院は、ほかに例を見ない独特の回廊で知られていますが、中でも柱頭の彫刻が見ものです。扱われている題材は、聖書からとった物語、修道院での生活、奇怪な動物などさまざまです。作者についてはロマネスクの常で、確かなことはほとんど何も分かっていません。ただ、作品の質やスタイルの違いから判断して、時代を異にする少なくとも二人、もしくは二つ以上の工房の手になるものであろう、というのが通説です。
そして12世紀ころと推測される初期の作品を手がけた石工を「サンフアン・デラ・ペーニャのマエストロ」(Maestro de San Juan de la Peña)と呼んでいますが、大きな目をむく人物像は、いちど見たら忘れられない、不思議な迫力に満ちています。
なお回廊は17世紀の大火で甚大な被害をこうむり、そのあと長らく修道院自体が見捨てられた状態だったこともあり、教会に隣接している回廊の北側部分には全く何も残っておらず、また岩山に近い東側もその大半が消滅しています。残りの部分も修復の手がはいっているため、柱頭の位置など果たして創建時の通りかどうか、判然としないところがあります。
しかし実際に柱頭彫刻の前に立ってみると、やはり噂にたがわず迫力のある作品が多いのに感服しました。20個を越える柱頭彫刻の中から、私が特にひかれた7個を選んでご紹介しようと思います。この7個の作品全てが、同じマエストロの手になるとの確証はありませんが、その点はさておき、若干私の独断をまじえて補足説明を加えておきます。
アダム(Adam)
IMG_1637Adam+Curve,+Sa%2B20,+5.3x3.jpg) (21)アダム(Adam)
(21)アダム(Adam)旧約聖書のアダムとイブの物語を題材にしたものですが、左隣に立っているはずのイブは、脚の部分を残してすっかり削り取られています。妖艶なイブの姿態が修道院にはふさわしくない、と判断された時代があったのでしょうか。
ヨセフの夢
IMG_4506+El+sue%C3%B1o+de+San+Jos%C3%A9.jpg) (22)ヨセフの夢(Joseph's Dream)
(22)ヨセフの夢(Joseph's Dream)イエスの父ヨセフが眠っているとき天使が夢に現れ、「起きて、子供とその母親を連れて、エジプトに逃げ、わたしが告げるまで、そこにとどまっていなさい。ヘロデが、この子を探し出して殺そうとしている。」(『マタイ福音書2-13』)と告げた場面です。
マエストロは、記憶に刻みつけてある福音書のこの一節を繰り返し口にしながら、のみをふるったに違いありません。大変な事態になりそうなお告げを聞くヨセフを、あくまで安らかな表情に仕上げたマエストロは、やはり神の手に全てを委ねることのできた時代の人だったと思います。
カナでの婚礼
IMG_1516+Las+bodas+de+Cana%C3%A1+4.7x4.jpg) (23)カナでの婚礼(Wedding at Cana)
(23)カナでの婚礼(Wedding at Cana)ガリラヤ地方のカナの町で結婚式に招かれ、水をぶどう酒にかえた、というイエスの初めての奇跡を題材にしたもので、「イエスが、水がめに水をいっぱい入れなさい、と言われると、召使いたちは、かめの縁まで水を満たした。」(『ヨハネ福音書 2-7)』)にあたる場面です。
ラザロの死
IMG_1517+Ma+Magdalena.jpg)
(24)ラザロの死(The Death of Lazarus)
この作品についてはさまざまな解釈があります。ここでは、イエスがエルサレム近くのベタニアを訪ねたとき、友人ラザロの姉妹マリアが、せっかくのイエスの来訪がラザロの死にまにあわなかったことを、イエスにとりすがって嘆いた場面、という解釈に従っておきます。
『マリアはイエスのおられる所に来て、イエスを見るなり足もとにひれ伏し、「主よ、もしここにいてくださいましたら、わたしの兄弟は死ななかったでしょう」と言った。イエスは、彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え、興奮して、言われた。「どこに葬ったのか。」彼らは、「主よ、来てご覧ください」と言った。イエスは涙をながされた。』(『ヨハネ福音書11-32-35』)
このあと、ラザロがイエスの手で生き返る、という奇跡が起きるわけですが、その場面は隣の柱頭に彫りこんであります。
もともとは彩色がほどこしてあったものらしく、色塗りの跡がかすかに残っているのが目に付きます。マリアの鼻が欠けているのはちょっと残念ですが、イエスもそして杖を手にイエスに従う二人の弟子も無傷のようです。
ロマネスク彫刻の説明に能を引き合いに出す意見を目にしたことがあります。ちょっとした動作や背景の違いで、人物の性格や状況、あるいは時の流れを象徴的に表現する能は、ロマネスク彫刻の象徴的な表現に通じるものがある、という見方です。
ロマネスク美術の素朴なところがいい、という人は結構いますが、この彫刻を眺めていると、素朴なというよりもっと何か深いもの、いろいろな約束ごとを踏まえたうえで、極力説明をはぶいた簡潔な表現が持つ力強さ、とでも言うものを感じます。
わずか数十センチの柱頭スペースに、誰もが熟知している聖書の物語を刻むにあたって、マエストロはよほど考え抜き、説明しなくても分かる部分はすっかり削り落としたうえで、骨太のエッセンス部分だけを刻み付けようとしたのではないでしょうか。
大理石より硬い地場の石材を使わざるを得なかったスペインの石工たちは、あまり細かい細工は得意でなかったなど、技術的な制約もあったかのも知れませんが、私はむしろ、大きな筆で一気にぐいっと一本の線を引くような力強さを愛でた人たちではなかったか、と想像するわけです。
エルサレムに迎えられる
IMG_1521+Jes%C3%BAs+entra+en+Jerusal%C3%A9n.jpg) (25)エルサレムに迎えられる(The Triumphant Entry into Jerusalem)
(25)エルサレムに迎えられる(The Triumphant Entry into Jerusalem)イエスとその弟子たち一行がエルサレムに近づくと、群集はイエスを預言者、あるいは救世主として歓呼の声で迎えますが、そのときイエスは、やがてその人たちの期待を裏切る結果になるだろうこと、そしてまた自らが十字架にかけられる運命にあることも見通していた、という場面です。この作品をマエストロの最大の傑作と評価する人もいます。
「弟子たちは行って、イエスが命じられたとおりにし、ろばと子ろばを引いて来て、その上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。大勢の群集が自分の服を道に敷き、また、ほかの人々は木の枝を切って道に敷いた。」(『マタイ福音書21-6-8』)
最後の晩餐
IMG_1674++La+%C3%9Altima+cena.jpg) (26)最後の晩餐 (The Last Supper)
(26)最後の晩餐 (The Last Supper)最後の晩餐の場面を描いたものとしては、15世紀末ころのダヴィンチの作品が最も有名ですが、この柱頭彫刻は食卓の席順や、イエスと使徒たちの動きに独特なものがあります。ふつうはパンを裂くはずのイエスが、となりのユダに何かを与え、ユダが裏切り者であることを示そうとしている、というのが通説のようです。そしてイエスにもたれかかって居眠りしているらしいのがヨハネ、そのさらに右からヨハネの肩に手をやり、ゆり起こそうとしているらしいのがペテロとされています。
このヨハネは福音書や黙示録の作者で、イエスに最も愛された一人と言われます。説教するイエスのとなりで居眠りをするなど、この彫刻以外にもヨハネの居眠りの場面はいろいろほかにも例があるようです。聖書には食卓の席順など詳しい状況説明があるわけでもないため、それぞれが独自の解釈で晩餐の場面を描くわけですが、最後の晩餐は列席者の間で騒がしいほどの議論があった、という解釈もあります。イエスの左隣にユダを座らせ、晩餐の席で居眠りをするヨハネを刻んだマエストロは、何を語りたかったのでしょうか。
この作品もやはり彩色をほどこした名残が見られますが、写真を撮る立場から言えば、もう少し磨いてホコリをとってくれると見栄えがするのに、という気持ちです。これも忘れがたい作品のひとつです。
石工たちの争い
IMG_4513+Fight+of+masons.jpg)
(27)石工たちの争い(Struggle among stonemasons)
これは聖書とは全く関係のない話で、二人の男が争っている場面です。ツルハシのような道具で相手をなぐりつけているのは、あるいは工事現場で実際にあった場面を再現しているのかも知れません。
サン・フアン・デラ・ペーニャのマエストロに限らず、11-12世紀ころの石工たちは、西ヨーロッパ全体が発展期にある時代を生きた人たちでした。「生活は楽ではないし、まだあちらこちらでいくさは続いているが、だんだん世の中も落ち着いて来た。ひと昔まえに比べればいい時代になった」ということを、多くの人々が実感していた時代です。そして、発展期の社会は、将来は明るいという楽観的な見方を育てます。さらに言えば、たとえ毎日の生活が苦しく、与えられた題材が暗い話であっても、全てを笑い飛ばし一心に石を刻む、勢いあふれる石工が良しとされた時代ではなかったかと思います。特に11-12世紀のスペインはいわば戦国時代で、一介の騎士の出でありながら、キリスト教領主とイスラム勢力の間をうまく泳ぎ、最後はバレンシア国の主に登りつめたエル・シッドのような人物が出た時代です。そんな時代が、底抜けに明るい豪快な作品を生み出したのではないでしょうか。
ロマネスク絵画で、殉教者の拷問・処刑などの場面が、ゴシック以降ほど陰惨なものにならないのは、そのことと関係があるような気がします。いかなる苦難に遭遇しても、それを神の試練だと考えることのできる人たちは、たとえ戦乱の時代にあっても将来への希望を失わなかったのだと思います。絶望感や時代の閉塞感とは無縁の底抜けに明るい石工たちが、何ものにもとらわれずぞんぶんに腕をふるった作品が教会を飾り、多くの人たちがまたそれを良しとした時代、それがスペインのロマネスク時代ではなかったか、とマエストロの作品を眺めながらつくづく思うわけです。
(Summary of the article)
The Romanesque Monastery of San Juan de la Peña
This spectacular monastery is located about 20 km west of the Cathedral of Jaca which was introduced in the last blog article(July18, 2010). The monastery is built into a huge rock at an altitude of over 1,000 meters. The name of the monastery means ''Saint John of the Rock''
The monastery appears on historical documents of the10th century, but a legend says that it was preceded by a group of hermits living in a cave of the rocky mountain since 7th century.
The monastery, same as the cathedral of Jaca, grew during 11th century under the patronage of Kingdom of Aragon, especially during the time of King Sancho Ramirez (reign 1063-1094). The monastery was appointed as the Kindom's royal pantheon and became well known as one of the monasteries on the pilgrimage route of Camino de Santiago. The famous cloister was added during 12-13 century
A big fire occurred in February 1675 which lasted three days and practically destroyed the monastery. A new monastery building was constructed short after that at another location about 1.5 km from the old monastery. In 2007 the new monastery building was transformed into a 4 star hotel and the historical museums of Kingdom of Aragon and the Monastery.
The monastery is composed roughly of two parts; the lower church of 10th century pre-Romanesque style, and the upper church of Romanesque style with an impressive cloister under the huge rock. The cloister was built during 12-13 centuries and contains a series of magnificent capitals carved by so called ''Master of San Juan de la Peña''. Practically nothing is known of the ''Master'' who could have been a group of excellent stonemasons who, during middle ages, did the job of masons, carvers and sometimes architects. Due to significant difference of style and quality among the capitals it is believed that the work was carried out by at least two different ''Masters'' during different periods, being the first one named as the ''Master of San Juan de la Peña''
The 7 capitals shown above are what impressed me most among over 20 capitals of the cloister.
One art critic says that we should pay attention to symbolic expressions employed by the Romanesque artists, especially by carvers, in a similar way as when we watch the Japanese Noh play in which a subtle inclination of the face could mean a great emotion, a short walk could mean miles of trip etc.