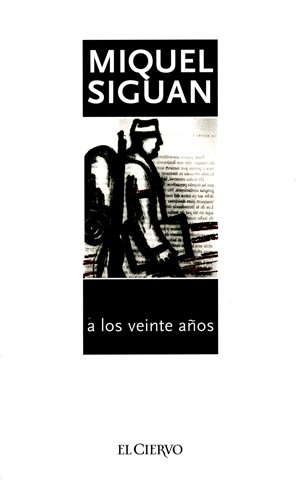スペイン地図-クリックして拡大(Click to enlarge)
(For the summary in English please see the end of this article)
 (1)修道院への道(On the road to the Monastery)クリックして拡大(Click to enlarge)
(1)修道院への道(On the road to the Monastery)クリックして拡大(Click to enlarge)サントドミンゴ・デ・シロス修道院
麦畑を両側に見ながら、ときには羊の群れとすれ違ったりする田舎道をゆっくり走っているうちに、スペインロマネスクの傑作で、いまも現役のベネディクト派修道院があることで有名な、サントドミンゴ・デ・シロスの町に着きます。マドリッドから240km、ブルゴスからは60kmの距離です。
(2)修道院遠景(View of the Monastery)クリックして拡大(Click to enlarge)
私たちが修道院を訪ねたのはことし3月の半ばでしたが、日中の気温は零度よりあがらず、町の広場の水汲み場には氷が張るほどの寒い日でした。イースター休暇の前で観光客はもともと少ない時期でしたが、例年にない寒さに人出が全くとだえてしまったようで、私たちが修道院の拝観を終え、暖をとるため目の前にあったバル(bar)に駆け込んだとき、バルの女主人は「きのうはお客がひとりも来なかった、きょうもあなたちだけかもしれないね」となげいていました。
人口300人の田舎町には不釣合いなほど広々とした駐車場が町の入り口にあり、大型観光バスや何百台もの車が殺到しても大丈夫という感じですが、私たちが着いたときには一台の車も見当たらなかったので、女主人がなげいたのも無理はありません。
 (3)凍りついたマイヨ-ル広場の水汲み場(Fountain at the Plaza Mayor)
(3)凍りついたマイヨ-ル広場の水汲み場(Fountain at the Plaza Mayor) (4)マイヨール広場から眺めた修道院(View of the Monastery from the Plaza Mayor)クリックして拡大(Click to enlarge)
(4)マイヨール広場から眺めた修道院(View of the Monastery from the Plaza Mayor)クリックして拡大(Click to enlarge)写真の奥に見えるのが修道院の教会部分ですが、有名な回廊への入り口は、教会の手前の坂を左にくだったところにあります。
(修道院の歴史)
サントドミンゴ・デ・シロス修道院が、前身のサンセバスティアン修道院の名前で史料に登場するのは10世紀のことですが、その当時すでによく知られた存在だったらしいことから、修道院の起源はさらに一世紀ぐらいさかのぼる9世紀末、すなわちレコンキスタ(再征服運動)と呼ばれるイスラム勢力とキリスト教徒領主勢力との戦いが、まだシロスの近辺でも続いていたころではないか、と推測されています。
10世紀の末ころ、コルドバに本拠をおくイスラムの勇将アル・マンス-ルの率いる軍勢が、東はバルセロナから西はサンティアゴにいたるまで、スペイン全土を荒らしまわった時期があります。そのときシロス修道院もその戦乱に巻き込まれ、壊滅的な打撃を受けてしまいました。そしてレオン国王フェルナンド1世(在位1037-1065)がその立て直しを聖ドミンゴに委嘱した1041年から、シロス修道院の再建が始まります。
聖ドミンゴは1000年ころの生まれといわれ、1073年に死ぬまでの32年間の院長在任中に、廃墟同然だったシロス修道院をスペイン有数のロマネスク修道院に仕上げた人物です。「ドミンゴ院長が祈れば全ての病気はそくざに治る」というたぐいの奇跡譚の主人公でもあり、戦乱時代の修道院長にふさわしい胆力と、高徳を兼ね備えたすぐれた指導者だったようです。その徳をしたって、レオン国王のほかエル・シッドなど地元カスティーリャ出身の貴族たちがすすんで領地その他の寄進に応じた結果、シロス修道院は財政面でも立ち直ります。
修道院があるブルゴスを中心とする旧カスティーリャ地方は、イスラム勢力の侵入路にあたったことからたくさんの城塞(castillo)が築かれ、そのため「カスティーリャ」と呼ばれるようになったという説があるくらい、もともとはレオン王国の辺境伯領でした。しかし、レコンキスタの進展とともに辺境領だったカスティーリャがしだいに重要性を増し、レオン・カスティーリャ王国として11世紀ころからスペイン政治の中心に躍り出てくるわけです。
ドミンゴ修道院長は死後3年目の1076年に聖人に列せられ、サントドミンゴ修道院と名前を変えたシロスの修道院には、聖ドミンゴの遺骸に詣でる巡礼者が殺到するようになりました。ちょうどサンティアゴ巡礼がヨーロッパ全体で急激に伸びた時代でもあります。そして、ドミンゴ院長のあとをついだ修道院長にも有能な人材が輩出し、スペインにおけるベネディクト派修道院のなかで、宗教面でも文化面でもつねに存在感を持つ修道院でした。また11世紀末から12世紀にかけては、有名な回廊建設にくわえて、「ベアトゥス黙示録注解」彩飾写本の制作など、宗教芸術の分野でもロマネスクの歴史に残るみごとな作品を残しています。
スペインのロマネスク教会や修道院にはよくあることですが、シロス修道院も19世紀半ばにいちど閉鎖され、長年の歴史が中断されましたが、幸い19世紀末にフランスのベネディクト派修道会の修道者たちの手で再建され、今日にいたっています。
私はこの数年間にスペインのロマネスク修道院をいくつか訪ねましたが、カタルーニャのモンサラット修道院をのぞけば、あとはすべて修道院跡ばかりでした。スペインでもサントドミンゴ・デ・シロス修道院のように、ロマネスク時代をしのばせる現役の修道院はごくわずかで、たいへん貴重な存在です。
(回廊)
シロス修道院の回廊が「スペインで最も美しい回廊」といわれるのは、11-12世紀の彫刻が見事に保存されていることのほかに、そこでいまもなお32人の修道士が、中世からのベネディクト会則に従う厳しい修道生活を送っていることと無関係ではないと思います。シロス修道院には、「ほんもの」のみが持つ、ある種の緊張感があります。そしてこの張りつめた空気と見事な彫刻とがあいまって、シロス修道院の回廊に一歩足を踏み入れた者を感動させるのだと思います。
私はこの回廊をご紹介する写真を全てモノクロームに変換することにしました。張りつめた空気はとても写真になりませんが、少なくとも浮き彫りや柱頭彫刻については、白と黒のコントラストだけのモノクロ画像が、シロス修道院の回廊で私が感じたものに近いと思うからです。

(5)東廊下からの眺めCloister(view from the east corridor)クリックして拡大(Click to enlarge)
 (6)北廊下の眺めCloister(view of the north corridor)クリックして拡大(Click to enlarge)
(6)北廊下の眺めCloister(view of the north corridor)クリックして拡大(Click to enlarge)
(7)西廊下からの眺めCloister(view from the west corridor)クリックして拡大(Click to enlarge)
 (8)西廊下の柱頭Cloister(capitals of the west corridor)クリックして拡大(Click to enlarge)
(8)西廊下の柱頭Cloister(capitals of the west corridor)クリックして拡大(Click to enlarge)回廊は、四辺形の一辺が30米をこえるずいぶん大きなもので、しかも2階建てになっています。ただし拝観がゆるされるのは1階の部分に限られます。1階の回廊の四隅にほぼ等身大の浮き彫りパネルが2枚ずつはめこまれ、合計8枚の大きな石のパネルに新約聖書の物語が浮き彫りになっています。柱は合計64本で、それぞれに柱頭彫刻がほどこしてあります。絵柄はさまざまですが、植物や奇怪な動物を、象牙細工のような細かな彫りで仕上げた作品の多いのが、シロスの特徴です。
回廊拝観の順路は、入り口から見て右手にあたる東側通路から始まり、時計と逆回りに北、西、南と回るのがふつうです。西廊下の途中で作風が変わるところから、二人の石工の作とするのが通説です。そして全く作者の名前が分からないため、前半を担当したのが初代のマエストロ(11世紀末ころ)、後半を二代目マエストロ(12世紀初めころ)と呼ぶことにしています。
(浮き彫りパネル)(Reliefs by the first maestro)
8枚の浮き彫りのうち6枚が初代マエストロの作品とされています。その中からとくに有名な3枚を選びました。浅い浮き彫りで細部が大事だと思われるため、一部拡大した写真を添付しておきます。いずれも11世紀末の作品とされているものです。
 (9)十字架降下(Descent from the Cross)クリックして拡大(Click to enlarge)
(9)十字架降下(Descent from the Cross)クリックして拡大(Click to enlarge) 
(10)十字架降下(Descent from the Cross)クリックして拡大(Click to enlarge)
画面の左に、イエスの傷ついた手にそっと頬をよせる聖母マリアを配し、その深い悲しみとマリアのやさしさを描こうとしたマエストロは、やはりロマネスクの人だったと思わせる作品です。プラド美術館にある、15世紀フランドルの画家ヴァン・デル・ヴァイデンの名画では、聖母マリアは気絶しています。時代が下るにつれ、しだいにドラマティックな描写になるようです。
 (11)エマウスの弟子たち(Disciples at Emmaus)クリックして拡大(Click to enlarge)
(11)エマウスの弟子たち(Disciples at Emmaus)クリックして拡大(Click to enlarge)  (12)エマウスの弟子たち(Disciples at Emmaus)クリックして拡大(Click to enlarge)
(12)エマウスの弟子たち(Disciples at Emmaus)クリックして拡大(Click to enlarge)イエスが復活して、エルサレム近くのエマウスで二人の弟子の前に現れた、というルカ福音書の場面です。この逸話はイエスの弟子たち、すなわち使徒たちの深い宗教体験を象徴するものだといわれます。帆立貝を縫い付けたサンティアゴ巡礼者の衣装を身にまとうイエスの姿に、シロスの修道士たちは、親しい永遠の同伴者を見たに違いありません。
厳しい修道生活に疲れたとき、あるいは信仰に迷いが生じたとき、この浮き彫りの前にたたずむ修道者の姿を、私は思い浮かべます。ロマネスクの時代には、シロス修道院の彫刻は単なる装飾ではなく、それは修道者が目には見えぬ神を身近に感じるための、架け橋のようなものであったはずですし、またいまもそうだろうと思います。シロス修道院の彫刻作品の迫力は、そこにあるという気がします。
 (13)不信のトマス(Incredulous Thomas)クリックして拡大(Click to enlarge)
(13)不信のトマス(Incredulous Thomas)クリックして拡大(Click to enlarge) (14)不信のトマス(Incredulous Thomas)クリックして拡大(Click to enlarge)
(14)不信のトマス(Incredulous Thomas)クリックして拡大(Click to enlarge)ヨハネ福音書にある、復活を信じない使徒トマスが、イエスの脇の傷口に手を触れている場面です。初代マエストロは、この場面にはいあわせなかったはずの聖パウロを、イエスの向かってすぐ右隣りに配しています。生前のイエスに会ったこともなければ、当初はユダヤ教のラビ(律法学者)を志し、キリスト教徒迫害に回った過去をもつ聖パウロを、イエスにもっとも近い弟子として描くことで、見ても信じないトマスとイエスを見ずして信じたパウロを対比させているわけです。
聖パウロへのかくべつの思い入れと、そしてマエストロが「信ずる」ということについて、深く考えをめぐらす人であったらしいことをうかがわせる作品です。初代マエストロは修道士ではなかったか、と私が考えるひとつの理由です。
(柱頭彫刻)
64個の柱頭彫刻は、初代マエストロと二代目マエストロの作にほぼ等分される、というのが定説です。その中からいくつかの作品をご紹介します。
初代マエストロの柱頭彫刻(Capitals by the first maestro)

(15)植物文様(Vegetable pattern)クリックして拡大(Click to enlarge)
 (16)獅子の頭を持つ怪鳥(Mystical birds)クリックして拡大(Click to enlarge)
(16)獅子の頭を持つ怪鳥(Mystical birds)クリックして拡大(Click to enlarge) (17)怪獣像(Mystical animals)クリックして拡大(Click to enlarge)
(17)怪獣像(Mystical animals)クリックして拡大(Click to enlarge)初代マエストロの柱頭彫刻は、ごくまっとうな植物文様もありますが、奇怪な鳥や動物を装飾化した図柄がたくさん目につきます。異様な図柄の説明は、ペルシャじゅうたん、オリエントの織物、装飾写本の挿絵などからヒントを得たという説、彫刻家の遊び心をあげる説、また全ての絵柄が悪との戦いなど何らかの象徴であるという説、とさまざまです。
たしかに、現代の私たちにはただ異様なものとしか映らない図柄にも、ちゃんとした出所があり、またそれぞれが何かの象徴であるのかも知れません。しかし奇怪な動物を描いた柱頭彫刻で回廊を飾ることが、世俗との関係を絶ち、物質や肉体の欲望を超克しようとする修道士たちに、いったいどんな意味を持っていたのか、という素朴な疑問が残ります。当時の修道院関係者の間でもきっと議論を呼んだに違いありません。
年代はさらに何十年もあとの話ですが、12世紀に革新的修道会として発展したシトー修道会は、宗教芸術を修行のさまたげとみなし、その価値を否定します。そしてそこから、教会には木の十字架のほか装飾的なものはなにも置いてはならない、という禁欲的なシトー会則が生まれます。
初代マエストロは、スペインのロマネスクではめったにお目にかからない、象牙細工のようなこまかな彫りをみごとに硬い石に刻む腕を持った人でした。しかし浮き彫りの制作では、テーマが新約聖書の物語という周知の内容であること、それに8枚組みパネルのような大作では絶対に失敗がゆるされぬため、新しい試みは極力さけ、技法面でも手堅く手馴れた彫りに徹したはずです。
しかし、柱頭彫刻の場合には、自らの能力の限界に挑戦する覚悟で、新しいテーマや技法に命がけで取り組んだと思います。30数個の作品の中には、彫り進むうちにつぎつぎとアイデアが浮かび、自然にノミが動いてどんどん図柄が変化していったような作品があったかもしれません。シロス修道院回廊の柱頭彫刻は、初代マエストロが修道士たちに向かって投げかけた、正解のない永遠の問い、常識への挑戦ではなかったのでしょうか。
これだけ優れた腕をもつ初代マエストロですが、その作品はシロス修道院いがいには見あたらないようです。中世の工人たちは定住せず、仕事を求めて遍歴の生活を送るのが常だったといわれるだけに、ふしぎなことです。しかし、もし初代マエストロが修道士であれば、修道院を出ることはできなかったわけで、その点もマエストロが修道士ではなかったかと私が想像する理由です。
二代目マエストロの柱頭彫刻(Capitals by the second maestro)
初代マエストロは回廊の完成を見ずして亡くなったようです。そしてそのあとをついだ二代目のマエストロは、初代が残した作品との連続性に留意しながら、独自の展開を図ります。二代目マエストロもたいへん優れた腕の持ち主でした。そしてその活躍の時期にあたる12世紀は、スペイン各地でロマネスク芸術がいっせいに花開き始めたころでした。
 (18)編み籠文様(Basketwork pattern)クリックして拡大(Click to enlarge)
(18)編み籠文様(Basketwork pattern)クリックして拡大(Click to enlarge)二代目マエストロも奇怪な動物の柱頭彫刻をたくさん彫っていますが、こんなすなおな編み籠文様の作品もあります。
 (19)エジプトへの逃避(Escape to Egypt)クリックして拡大(Click to enlarge)
(19)エジプトへの逃避(Escape to Egypt)クリックして拡大(Click to enlarge)これはマタイ福音書にある、聖母マリアがイエスを懐に抱いてエジプトに逃れる場面です。二代目マエストロが、いかにもロマネスクらしい温かみのある人物などの描写に秀でた人だったことを、うかがわせる作品です。

(20)教会(Church of the monastery)クリックして拡大(Click to enlarge)
修道院の教会部分は、18紀にロマネスク教会を取り壊して、ネオクラシック様式にすっかり改装されてしまいました。惜しいことをしたと思います。しかし途中で改装資金が続かなくなり、回廊部分はロマネスク建築がそのまま手つかずで残ったのだそうです。
 (21)CD of the Gregorian Chant by Choir of the Monasteryクリックして拡大(Click to enlarge)
(21)CD of the Gregorian Chant by Choir of the Monasteryクリックして拡大(Click to enlarge)シロス修道院のグレゴリオ聖歌隊は有名で、EMIからCDが出ています。礼拝の時間には美声を聴かせてくれるそうですが、残念ながら私たちはその機会に恵まれませんでした。
シロス修道院には宿泊所があり、外部の者にも修道院の生活を垣間見る機会を与えてくれる仕組みがあります。修道院のウェッブサイトによれば、受け入れの条件は男のみ、滞在日数は3日から8日の間、費用は食事つきで一泊38ユーロ(約4千円)となっています。
スペインのロマネスク修道院の多くが観光の対象となり、まるで博物館のようになりつあるなかで、中世の伝統と遺産を守りながらしかも開かれた修道院をめざす、サントドミンゴ・デ・シロス修道院には感服しました。
(Summary in English)
The Romanesque abbey of Santo Domingo de Silos, a Benedictine monastery known for its cloister and Gregorian Chant, is located in the land of Castilla, about 240 km of Madrid, 60 km from Burgos. The origin of the monastery is estimated to be during the late 9th century when the area used to be the battle field of the ''Reconquista'' (war of Spanish Christian lords against Islam rulers).
In 1041 Santo Domingo(Saint Dominic) was appointed by King Fernando I of Leon as the prior of the monastery which had been ravaged by Islam forces led by Al-Mansur who conducted incursions all over Spain from Barcelona to Santiago during the late 10th century. Prior Domingo not only achieved the reconstruction of the monastery during his 32 years of tenure but also made it one of the most important centres for spiritual and cultural activities in Romanesque Spain. The monastery is famous for its 2 story cloister which is decorated with the most beautiful stone carvings of the time. Also it is known for an illuminated manuscript copy of '' Beatus commentary on the Apocalypse'' now owned by the British Library, or enamelwork which preceded to those of Limoge.
In 1076, three years after his death, prior Domingo was canonized and became Santo Domingo. The monastery was named after the saint and a flood of pilgrims started arriving to visit the saint's remains. It was also the time when the pilgrimage to Santiago de Compostela got a big boost all over Europe.
The monastery was consecrated in 1088 but the construction continued. It is believed that the 2 carvers worked on the decoration of the cloister. As is common with Romanesque art nothing is known of these artists. One is called ''the first maestro'' and another ''the second maestro''
The first maestro made 6 out of 8 large reliefs which are placed one pair at each corner of the cloister. Out of 64 capitals the first maestro apparently made the first 30 something during the 11th century and the rest was done by the second maestro during the early 12th century. Both are excellent artists, but the first maestro is outstanding in carving on hard stones with fine details like ivory carving which is uncommon in Spanish Romanesque especially in late 11th century.
We visited the monastery in an early hour of March, 2010. It was a very cold and overcast day. There were no other visitors and the silence was the word to describe that morning in the cloister.
Only the lower cloister was open for the public visit. Santo Domingo de Silos is one of the few Romanesque monasteries in Spain where monks are still leading a monastic life. There was something genuine.
I've decided to convert the photos of the cloister into black and white, because no color matches to what I saw and felt on that day in the cloister.


















Map+a+de+Espa%C3%B1a-San+Juan+de+la+Pe%C3%B1a(PSD)+Sep+16,+2010.jpg)
IMG_4461+4x6(800+pix).jpg)

IMG_1614+Parador+3x4(600+pix).jpg)
IMG_1496Camino+al+monasterio+viejo+4x4.2(600).jpg)
IMG_4702+Vista+de+arriba+de+Iglesia-Claustro,+Sa%2B15.jpg)
IMG_4746+Fachada+Dist,+Curve,sa%2B10+3x4.5.jpg)
IMG_4608+Iglesia+vieja+4x2.8.jpg)
IMG_4631+Altarles+dobles+2.8x4.3.jpg)
IMG_4624+Pintura+mural.jpg)
IMG_1566+Patio-Pante%C3%B3n+de+nobles+USM(20),.jpg)
IMG_4602++Nichos+del+nobels.jpg)
IMG_4601+Crismon+USM(40),+Curve,.jpg)
IMG_4482+Vista+hacia+el+altar+central.jpg)
IMG_4496+Apse+USM(70),.jpg)
IMG_4639+Ceiling++USM(60),.jpg)
IMG_4600+Puerta+moz%C3%A1rabe+hacia+claustro.jpg)
IMG_4576+Puerta+moz%C3%A1rabe.jpg)
IMG_4583+El+Claustro+USM(20),+Curve,+Sa%2B10,+C-20,.jpg)
IMG_4539+El+Claustro(resto+de+pared).jpg)
IMG_4536+Un+arco+del+lado+sur3.5x5(600).jpg)
IMG_1637Adam+Curve,+Sa%2B20,+5.3x3.jpg)
IMG_4506+El+sue%C3%B1o+de+San+Jos%C3%A9.jpg)
IMG_1516+Las+bodas+de+Cana%C3%A1+4.7x4.jpg)
IMG_1517+Ma+Magdalena.jpg)
IMG_1521+Jes%C3%BAs+entra+en+Jerusal%C3%A9n.jpg)
IMG_1674++La+%C3%9Altima+cena.jpg)
IMG_4513+Fight+of+masons.jpg)