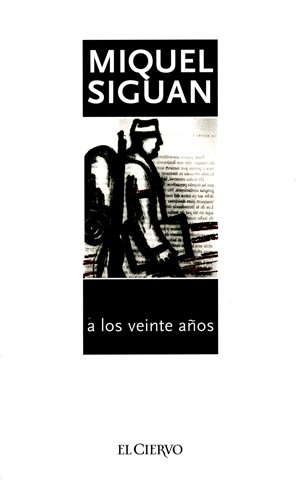―フランコは人間性に対する罪で裁かれるべきなのか?―
スペイン内戦とそれに続いたフランコ独裁体制の下で、体制にとり好ましからざる人物と見なされ、不法拘禁されたまま行方が分らなくなっているスペイン人の数は10万人を越えると推定されています。そしてその内の多くは内戦の渦中で正当な裁判を経ることもなく銃殺され、スペイン各地にある共同墓地とは名ばかりの土中に埋められたままになっているのが現状のようです。そしてこのフランコ体制の犠牲者たちは、内戦から70年が過ぎた今も正式に死亡が確認されることもなく、未だに「強制連行による行方不明」の状態にあります。
これらの犠牲者たちの肉親はその殆どがもう子供や孫の世代ですが、二年前からマドリッドの全国管区裁判所に対し20件を越える訴えを重ねていました。その趣旨は、内戦中と内戦直後のフランコ将軍とフランコ体制の指導者は、体制と意見を異にする市民を計画的に抹殺したのであり、それは「人間性に対する罪」を犯したものとして裁かれるべきこと、また共同墓地に埋葬されている筈の肉親を葬るために遺体の発掘と鑑定を求めるという内容です。
これらの訴えを裁判にかけるべきかどうかを予審判事として検討して来たのが、チリのピノチェット元大統領を逮捕しようとして有名になった全国管区裁判所中央予審部のバルタサル・ガルソン判事です。
ガルソン予審判事は10月16日付けで、フランコ将軍とフランコ体制の当時の指導者30数名が、人間性に対する罪を犯したか否かに関し捜査を進めること、また同時に19箇所の共同墓地での遺体発掘を認める、との決定を下しました。その中には詩人で内戦が始まってすぐ殺されたガルシア・ロルカが埋葬されているという、南スペインのグラナダ郊外にある共同墓地も含まれています。
ガルソン判事の決定は犠牲者の家族にとっては朗報ですが、スペインの世論がこれを圧倒的に支持するかとなると、それはまた別問題だと思います。内戦に関する議論になると、未だにスペインでは国民の意見が真っ二つに割れるのが常ですが、特に内戦から70年、フランコの死から30年の時間が過ぎたいま「人間性に対する罪」で50年前のフランコ体制の指導者を裁こうとしても、国民のコンセンサスを得るのは至難のわざでしょう。「何でいまさら古傷に触るのか」、「時間と費用の無駄遣いだ」、「共和派の罪を裁かないのは片手落ちだ」という類の反応が見られます。
本来はガルソン予審判事と歩調をあわせるべき全国管区裁判所の検察部長が、過去の最高裁の判決などを根拠に、この訴訟は全国管区裁判所として取り上げられないとの意見を今年の二月に公にしています。その論拠は、内戦当時の刑法には「人間性に対する罪」の規定は存在しなかったこと、また殺人などの通常犯罪に問われる場合でも、内戦とそれに続くフランコ体制の軍人や官憲を免責にしている1977年の特赦法が適用されること、そしてもし仮に大量殺戮などの罪があったとしても、全国管区裁判所の管轄はスペイン国外の事件に限られること、などの理由を挙げています。
これに対するガルソン判事の論拠は、現時点でスペイン内戦を司法の立場で見直す意図はないが、同じ内戦の犠牲者でありながら、勝利者(フランコ)側の犠牲者には戦後、国がその被害につき詳しい調査を行い補償の措置が取られたにも関わらず、敗者(共和派)は拘禁のうえ拷問されたり、10万人を越える行方不明者が出るという、国としての不公平な扱いが特に1952年頃まで顕著であるのは否定し得ない事実であること。
また今に至っても「強制連行による行方不明」が存在するということは、法的には未だ居所不明の不法拘禁が現在も継続しているということであり、これについては人間性に対する罪の観点から責任者の刑事責任が検討されるべきこと、また1977年の特赦法は重大な人権侵害までを免責とするものではないことなどの理由で、フランコ将軍および当時指導的立場にあった30数名の軍人や政治家の名前を上げ、「強制連行による行方不明」に関しその刑事責任につき取り調べを行うこと、そしてこれら行方不明者の実態を把握するため、7名の専門家による審査グループと10名の司法警察官による捜査チームを立ち上げるとしています。そして司法がいつまでも沈黙を守り続けることは、本来刑事責任を負うべき者に事実上の免責を与えることになりかねない、とも述べています。
但しフランコ将軍はじめ名前の上がっている軍人や政治家の全員がすでに死亡している以上、実際に法廷で裁くことは不可能であり、実際にガルソン判事が今後どうやって予審から訴訟にまで展開して行くのか不明な部分が多々あります。また検察部長が予審判事と対立している現状などを勘案すると、捜査も難航が予想されます。しかし、犠牲者の家族の訴えを玄関払いにするような対応ではなく、いわば火中の栗を拾うような難問に取り組もうとしているガルソン判事の姿勢から、司法の社会的あるいは歴史的な責任とは何か、検事や判事は何のために存在するのか、という司法制度の根底に関わる問いかけを感じます。
1977年の特赦法は、翌年に制定される民主憲法の捨石のような形で、内戦にまつわる刑事責任はお互いに問わないという形で左右の政治勢力の妥協が成立し、血塗られた内戦の歴史の一部を封印したものでした。そして当時の軍部や保守派に、独裁制から民主国家に向けての急速な変化を容認させるためには、この特赦法が必要だったのだ、あれはスペイン民主化のための止むを得ざる対価だったのだ、と今でも多くのスペイン人が口にします。1970年代をスペインで過ごした私は、1975年にフランコが亡くなった時、軍部の動きにみんなが神経を尖らせていた、当時の緊迫した雰囲気を思い出すことがあります。70年代のスペインは内戦にまつわる忌まわしい記憶をお互いに封印することで、国民の和解を図ったとも言えます。しかし同時にそれはフランコ体制の犠牲者への償いを先送りしたことでもありました。
あれから30年が過ぎ内戦を生きのびた世代も残り少なくなり、いずれも90歳を越える時期になったいま、行方不明の肉親を何十年ものあいだ探し続けてきた内戦の犠牲者の家族に、やっと不十分ながら司法の目が向けられようとしているという感じがします。そして、司法の場でいろいろな事実が今後公開されるにつれて、フランコ体制の責任を問うという議論は、予審判事と検察部長の対立だとか今回の予審の成否というようなレベルを越えて、もっと大きな公開の場での議論を巻き起こすテーマになるのではないかと思います。
ひとつの国が、そしてその国民が人間らしさを失わないためには、たとえ忌まわしい戦争についての記憶であってもその封印を解いて記憶を共有し、お互いがそれを忘れないように努めること、そして未だに救いの手が差し伸べられていない犠牲者がいれば救いの手を差し伸べ、未だに葬られていない死者があればそれを葬ること、それはスペイン人にとっても避けて通れない道だろうという気がします。
2008年10月29日水曜日
登録:
コメント (Atom)