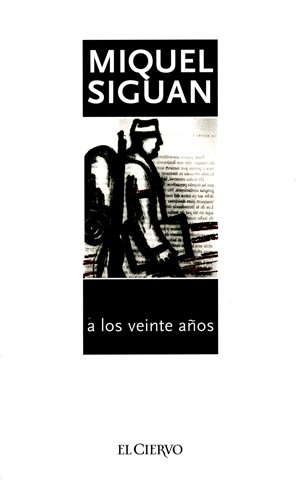スペイン内戦の写真家Agustí Centelles
スペイン内戦の写真家と言えば、大半の人はまずキャパ(Robert Capa 1913–1954)の名前を思い浮かべることだろうと思います。しかしカタルーニャの写真家アグスティ・センテーリャス(Agustí Centelles 1909-1985)は、撮影した写真の量においてもまたその質においても、キャパに勝るとも劣らない内戦の記録を残した人でした。
12月1日のスペイン各紙に、「Centellesの全作品、スペイン文化省が家族から70万ユーロで買い上げ」(現行レートで約9千万円)というニュースが載りました。1万枚を越えるネガフィルムは、そのほとんどが1930年代後半のスペイン激動の時代を記録した写真ばかりです。
Centellesは1909年にバレンシアで生まれ2歳の頃にバルセローナに移っています。家計を助けるため11歳で働き始め、学校に通ったのは一年ぐらい、あとは全て独学の人でした。子供の頃から写真に興味を持ち、新聞社のグラビア印刷部門でしばらく働いたあと、18歳でバルセローナの報道写真家Jopsep Badosaに弟子入りして写真家としての腕を磨きます。そして25歳(1934年)の時、分割払いで買ったライカ一台を手に報道写真家として独立しました。
+at+200pix.jpg) Leica IIIa, the most popular Leica in 30’s & 40’s.(Centellesが最初に買ったと推測されるLeicaIIIの改良型(外見は変わらず)
Leica IIIa, the most popular Leica in 30’s & 40’s.(Centellesが最初に買ったと推測されるLeicaIIIの改良型(外見は変わらず)Leicaが変えた報道写真
1920年代と30年代は、新聞がグラビア印刷を取り入れたり、米国のLife誌など写真主体の新しい週刊誌が誕生したりで、世界的に報道写真という新しい写真の分野が花開いた時期でした。
それにあわせるようにカメラの世界でも技術革新が進みます。1925年に第一号機が発売されたLeicaは、ボディーは堅牢な金属性、コートのポケットに入る小型サイズながら、既存の映画用35ミリ・ロールフィルムの採用により36枚の連続撮影ができること。またレンズ交換が可能で新聞写真サイズに引き伸ばせる解像度を持つ交換レンズが開発されるなど、従来のカメラのイメージを一変させる革命的な製品でした。そしてドイツの写真機業界では後発だったLeitz社を、一挙に小型カメラ業界のリーダーに押し上げた、ヒット商品でもありました。
第一次大戦の写真を見ると、戦場の兵士達はカメラの前でポーズをとっています。これは当時のカメラは三脚に固定し静止した被写体を撮るものだった、という技術的な制約もあったのでしょうが、肖像写真が主だった時代の写真観の反映でもあると思われます。
しかし高感度ロール・フィルムの開発と、ポケットに入れてどこにでも持ち運べるLeicaの登場により、動く被写体を追いかけるようなダイナミックな写真の撮り方が可能になります。そしてそれをスペインの戦場で実証したのがCapaやCentellesでした。
Centellesはスペインで最初にライカを使い始めた写真家の一人ですが、当時の新聞の編集者の中には、「そんなおもちゃみたいなカメラでは」と、頭から拒否した人もいたそうです。写真を一枚撮るたびにフィルムを差し替える必要のある大型カメラが、プロの道具と考えられていた時代の話です。

Centellesの代表作
La Fábrica社出版のスペイン写真家叢書(Biblioteca PhotoBolsillo, Madrid, 2006)の第15巻で、Centellesの主な作品が紹介されていますが、その表紙に使われている写真が彼の代表作のひとつです。
これは1936年7月19日にバルセローナ市内のDiputación通りで撮ったものとされていますが、共和国政府に対しクーデターを企てたフランコ派の反乱軍兵士を相手に、倒れた軍馬を盾に銃撃戦を展開している突撃警察隊員(guardia de asalto)の写真です。この日Centellesはライカを手に終日バルセローナ市内を駆けめぐり、反乱軍の決起から降伏までの激動の一日を記録しています。
 (Photo:courtesy of © Agustí Centelles, VEGAP)Anarchist soldiers leaving for Aragon front(Barcelona,July-1936)
(Photo:courtesy of © Agustí Centelles, VEGAP)Anarchist soldiers leaving for Aragon front(Barcelona,July-1936)バルセローナからアラゴン戦線に向かうアナキスト民兵部隊(1936年7月)
1936年の夏、Centellesは前線に向かう民兵部隊と共にフリーランスのカメラマンとしてアラゴン戦線に赴き、初期の民兵部隊の戦いを撮りました。1937年には共和国軍兵士として召集されますが、Centellesが手にしたのは銃ではなくカメラでした。東部方面軍政治コミサール本部所属の写真課員として、引き続きアラゴン戦線での戦闘や銃後のバルセローナの模様を記録しています。
 (Photo:courtesy of © Agustí Centelles, VEGAP)Victim of air-raid by Franco’s forces(Lerida Nov 2, 1937)フランコ軍によるレリダ市空爆の犠牲者(1937年11月2日)
(Photo:courtesy of © Agustí Centelles, VEGAP)Victim of air-raid by Franco’s forces(Lerida Nov 2, 1937)フランコ軍によるレリダ市空爆の犠牲者(1937年11月2日)Centellesは、戦意高揚や宣伝用のいわゆるプロパガンダ写真を撮らざるを得ない立場にありました。しかし共和国軍の写真課員として各地を飛び回るなかで、この夫の遺体を前に号泣する夫人の写真のような、見る者の心を打つ作品をいくつも残しています。この写真も彼の代表作のひとつです。
Centellesは、「死者の写真はクリーンに撮らなくてはならない」とよく口にしていたそうです。報道写真家は死者を悼む気持ちを失ってはいけない、と自らを戒める言葉でもあったのでしょう。
1937年から1938年初めにかけて、北はアラゴン州のピレネー地方から南はテルエルまで、各地の戦闘に従軍したCentellesは、バルセローナに呼び戻され、1938年4月付けで防諜組織の軍事情報局(SIM)所属の写真室長に就任します。実際にどんな業務だったのか詳しいことは分りませんが、のちにフランスに亡命しBramの強制収容所で書きとめた日記を中心とする『ある写真家の日記』(Diario de un fotógrafo, Ediciones Península, Barcelona, 2009)の中で、当時の状況に少し触れています。それから推測すると、フランス亡命に至るまでのバルセローナでの10ヶ月間は、街に出て報道写真を撮るよりも、むしろ内向きの仕事が多かったようです。
『ある写真家の日記』-フランス亡命の記録
 (Photo:courtesy of © Agustí Centelles, VEGAP)The Concentration camp at Bram(Aude)ブラムの強制収容所
(Photo:courtesy of © Agustí Centelles, VEGAP)The Concentration camp at Bram(Aude)ブラムの強制収容所1939年1月26日のバルセロナ陥落の前日、Centellesは妻と1歳半の長男を父親に託し、写真機材と数千枚にのぼる内戦のネガフィルムを入れた旅行カバンを抱えてフランス亡命の旅に出ます。40万人を越える避難民が殺到して大混乱の国境をやっとの思いで通り抜けましたが、すぐフランス官憲の手で悪名高いアルジュレス(Argèles-sur-Mer)の強制収容所に送りこまれてしまいました。そして一ヵ月後の3月初め、アルジュレスからさらに120キロぐらい内陸に入ったオード県ブラム町(Bram, Aude)の強制収容所に移されます。
Bramは中世の城壁都市として有名なCarcassonneから20キロぐらい西にあり、そこに新設された強制収容所には15,000人から17,000人ぐらいのスペイン人亡命者が収容されました。新設とは言っても、一戸あたり100人を収容する25m x 6mサイズの木造宿舎170戸を、鉄条網で囲んだだけのもので、暴動などを警戒してのことでしょうが、宿舎は15戸(収容者1500人)ごとに鉄条網で区切られ、お互いの行き来には制限があったようです。床に藁を敷いたものがベッド代わりで、暖房はむろんのこと電気もなく、写真で見ると宿舎というよりまるで大きな馬小屋という感じです。
Centellesの日記は1939年1月12日付けでに始まり、バルセローナでの生活ぶりと、家族を置いてひとりフランス亡命の旅に出る悩みを吐露した部分を含んでいます。しかし日記の中心は半年におよぶBram収容所での日常生活の描写です。将来の不安と寒さにさいなまれ、雑居生活に神経をすり減らしながら、バルセローナに残してきた家族のことを思うCentellesの心境や、苛立つ収容者たちがつまらぬことで言い争いを始めたりする姿が、いきいきと描かれています。
Centellesは収容所の中でも写真を撮り続け、有料で警護の警察官や仲間の肖像写真を撮っては、食費の足しにしたこともあったようです。
こんなBramでの生活が半年ばかり続いたあと、運よくCarcassonneのある写真館での仕事が舞い込み、Centellesは1939年9月初めに出所することができました。フランス軍に召集された写真館主の代役として忙しい毎日を過ごしているうちに、フランスは1940年6月末からナチスドイツの占領下におかれてしまいます。そしてやがて始まったレジスタンス運動にCentellesも協力することになり、写真館の地下に秘密の写真ラボを設け、身分証明書の偽造作成などを手伝いました。
しかし1944年1月、ナチスドイツ秘密警察(GESTAPO)の手でCarcasonneのレジスタンス運動関係者の一斉検挙が行われ、Centellesが親しくしていた友人たちもナチスの強制収容所送りになりました。そしてCentellesにもGESTAPOの手が伸びる恐れが出たため、スペイン警察に逮捕されるのを覚悟で、バルセローナに逃れる決心をします。
Centellesは、フランス亡命いらい片時も離さなかったネガ入りの旅行カバンをCarcassonneの下宿先の家主に預け、1944年4月ひそかにバルセローナ市に戻りました。そして家族と合流のうえ、親戚を頼ってタラゴーナ県レウス町に移り住み、パン屋の手伝いをしながら、一家揃って目立たないようにひっそりと暮らします。
内戦直後の混乱した世情が落ち着いたころを見計らって当局に自首し、1947年にはバルセローナに引っ越すことができました。しかし、報道写真家として活動することは認められず、当時38歳のCentellesは宣伝写真などを手がけながら商業写真家として生きてゆくしかありませんでした。
1万枚のネガ
1975年の独裁者フランコの死と共にスペイン民主化の動きが始まったのを見届けたCentellesは、1976年にCarcassonneに出向き、預けてあった数千枚のネガを全て持ち帰ります。こうして内戦の記録を含むCentellesの写真はぶじ散逸を免れたわけですが、1976年に始まったスペインの民主化が、なるべく過去の問題にはお互いに触れないようにしよう、内戦の記憶は封印しよう、という当時の風潮の中で進んだこともあり、Centellesが時には命を賭けて撮り、フランス亡命中も肌身離さず保管した、内戦の記録に対する世間の関心はいまひとつ盛り上がりませんでした。Centellesとその家族にとっては割り切れない思いだったろうと推測します。
Centellesを「スペインのCapa」と呼ぶときには、「世界的に有名なCapaに似た写真家」という理解がその裏にあるような印象を受けます。しかしCentellesはCapaの亜流ではなく、優れた報道写真家でした。ただスペイン内戦に限って言えば、Centellesは戦争を地道に記録した人であり、Capaは戦争に人間のドラマを見出した人だった、という違いを感じます。
Capaは限られた取材日数の制約の中で、ドラマ性のある写真を求めるジャーナリズムの期待に応える必要がありました。そして見事にその期待に応えたCapaにはほんとうに感服します。
しかし、兵士たちと寝起きを共にしながら戦場で撮ったCentellesの写真には、ホテルから車で戦場に駆けつける外国人のCapaには撮れないものがありました。それがCentellesの写真の魅力のひとつだと思います。
最近の新聞報道によると、カタルーニャ自治政府(Generalitat)の一部の人たちは、本来カタルーニャの文化遺産であるべきCentellesのネガを、家族がスペイン中央政府にカネで売り渡したと非難しているそうです。それに対する家族の言い分は、「Generalitatに本当にその気があるなら25年間も時間があった筈だ。しかし、Generalitatはけっきょく何もしてくれなかった。中央政府が買い上げるという話が出たので、急に名乗りをあげただけだ。しかも中央政府とは違って、これから写真をどう公開してゆくつもりなのかGeneralitatには何のアイデアもない。」と反論しています。
Centellesの家族にしてみれば、Christie’sなどオークション会社経由で高い値段で売却する道もあった筈ですが、作品の公開という点を重視し、スペイン政府文化省に譲渡することに決めたのは立派な見識だと思います。もし事実が報道の通りなら、カタルーニャの一部の人たちの批判は、ちょっと的はずれという感じがします。
ともかく貴重な内戦の記録が、コレクターの手に落ちることもなくスペイン政府の手に渡り、こんご一般公開が進む可能性が出てきたのは喜ばしいかぎりです。現状ではひとつひとつの写真についてのデータの整理が不十分のようで、同じ写真でありながら違ったタイトルがついたり、付記される撮影場所や年月日が異なったりするケースを見かけます。これを機会にCentellesの伝記の編纂や、全ての作品についての考証作業が進み、新しい写真集の出版が実現することを願っています。
Centelles生誕百年の今年は、スペイン内戦終結七十周年であると同時に、フランスの強制収容所開設七十周年でもあります。そんな背景もあってのことでしょうが、収容所のあったBram町で最近Centellesの作品展が開かれました。フランス人にとっては余り思い出したくない記憶でしょうが、ちゃんと過去の歴史に向き合おうとする姿勢に敬意を表します。
またスペイン政府の後押しでCentelles国際報道写真賞を創設する構想もある由で、「スペインのキャパ」ではなく、「スペインの報道写真家、Agustí Centelles」が、世界に知られる時代が来ることを期待します。
Agustí Centelles - Spanish photographer called Robert Capa of Spain
(Summary)
Agustí Centelles(1909-1985),a Spanish photographer famous for his photos of the Spanish civil war(1936-39),is often called ''Robert Capa of Spain''.
The Spanish press reported in early December that the Spanish Ministry of Culture had agreed to buy the Centelles’s entire collection of 10,000 photos, mostly of the Spanish civil war era, from the family at 700,000 euros.
According the press some members of the Cataluña’s autonomous government (Generalitat) have bitterly criticized the decision of the Centelles family for selling the photo collection to the Spanish central government alleging it’s a cultural heritage of Cataluña. The family reportedly responded to it saying that the Generalitat had 25 years, if they had really wanted to acquire it indicating also that the Generalitat had ignored the family’s plea of assistance in the past for safeguarding of the collection.
Agustí Centelles was born in Valencia in 1909 but moved to Barcelona at 2. He started the career as professional photographer at 18 as an assistant to Josep Badosa, a popular photographer at the time in Barcelona. In 1934 at the age of 25 Centelles started on his own with a Leica which he had bought on installments. He was one of the first Spanish photographers who used Leica when the majority of professionals were relying on large format cameras.
The Leica camera which was developed by Leitz in 1925 has changed the way of taking photos. Robert Capa and Agustí Centelles proved that a small and versatile 35 mm film camera (‘’like a toy’’ for some traditional press people) could make brilliant photos of the war.
On July 19, 1936, the day of failed military coup in Barcelona, Centelles took the famous photo of 3 militias in urban police uniform(Guardia de Asalto) who were exchanging fire with the rebels with dead horses used as barricade.
As a free-lance war photographer he then followed militia groups, mostly anarchists from Cataluña,who went to the Aragon front to fight against rebel forces led by general Franco. In 1937 Centelles was drafted by the republican government and was handed a Leica instead of a gun. As a military photographer he witnessed, sometimes risking his life, many battles and miseries of the civil war. One of his master pieces is the woman crying in front of the dead husband, casualty of the air-raid in Lerida city.
On January 25, 1939, the previous day of taking Barcelona by Franco’s forces, Centelles chose to go on exile to France leaving his family in Barcelona. He carried with him a small suite case filled with thousands of negatives of the war. He was one of those over 400,000 refugees who tried to escape to France during the two weeks after the fall of Barcelona. He managed to cross the border in chaotic situation but was detained by French police and was sent to the concentration camp established by French government, first in Argèles-sur-Mer, and a month later in Bram near Carcassonne.
We know how hard the life was at the camp through his diary(‘’A diary of a photographer, Bram 1939’’ ) which was published in Catalan and Spanish. Centelles comments in the diary that the French government treated Spanish exiles as if they were criminals. There was no electricity nor heating and the food was poor at the Bram camp for 15,000 exiles, which was considered to be a ‘’model’’ camp by the French government.
Fortunately for Centelles, in September 1939 he found a job at a photo studio in Carcassonne whose owner had been drafted by the French government. Centelles became a free man after 6 months of internment. But the freedom did not last too long. In June 1940 France was occupied by Nazi Germany and the French resistance movement started. Centelles collaborated with the resistance setting up a secret photo lab in the basement of the studio and made forged IDs for resistance members.
In January, 1944 GESTAPO arrested hundreds of members of resistance in Carcassonne including some of the best friends of Centelles who were sent to Nazi’s concentration camp. In view of possible persecution by GESTAPO Centelles decided to return to Barcelona risking the arrest by Spanish police.
In April, 1944 Centelles entrusted the suite case of his negatives to the care of the landlord in Carcassonne from whom he had rented the house and secretly returned to Barcelona. After joining the family he moved to the town of Reus(Tarragona province) where he had relatives and worked as a baker.
In 1947 Centelles turned himself to the police and moved to Barcelona. No criminal charges were laid on him, however Centelles was denied to work as a photojournalist, his specialty. Only choice for a 38 year old ex-photojournalist was to work as a commercial-industrial photographer which he did in the rest of his life.
In 1976 when the transition to democracy started in Spain one year after the death of Franco, Centelles went to Carcassonne and recovered his negatives. However, the attitude of majority of the Spanish people those days was; ‘’not to dig the past, try to forget the painfull memories of the civil war and reach the reconciliation’’. As a consequence the negatives which Centelles had made risking his life and kept as a treasure, did not receive the due attention from the public. It was a disappointment for Centelles and his family. He died in Barcelona in December,1985 at the age of 76.
A series of expositions of his work have been organized in Spain and in France as well. Currently an exposition is on going at the town of Bram as commemoration of 70th anniversary of the end of Spanish civil war and the start of internment of Spanish exiles. With the acquisition of the collection by the Spanish Cultural Ministry the public access to the Centelles’s work is expected to be improved and better organized including future expositions in those countries as USA where Centelles still remains mostly unknown.
.jpg)


.jpg)


.jpg)
.jpg)

,+C%2B10,+Sa%2B15.jpg)