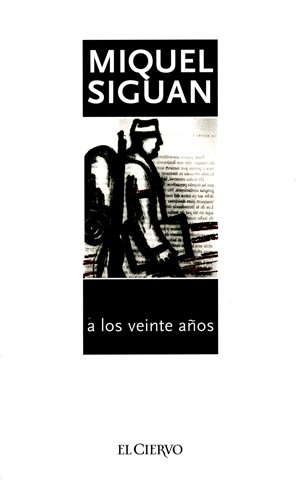―1977年の「特赦に関する法律」(Ley de Amnistía)―
前回は「歴史の記憶に関する法律」を話題に取り上げましたが、あの法律にちょうど30年先立つ1977年10月に、「特赦に関する法律」(Ley de Amnistía)が、まだフランコ体制の延長線上にあった当時の議会で成立しています。この「特赦法」は「歴史の記憶に関する法律」といわば表裏をなすものですので、1970年代後半にスペインで起きた民主化体制への歩み(これをtransiciónと称します)とからめて、その要点をごくかいつまんでお話してみましょう。
(独裁体制から民主主義体制へ)
1975年11月にフランコが死ぬと、スペインは独裁政治体制から民主主義体制に向けて大きく舵を切り始めます。38歳で国家元首を継承したフアン・カルロス国王も、そして1976年7月に首相に就任した44歳のアドルフォ・スアレスも、いずれも「フランコ体制」の出身者ではありますが、35年の長期に亙ってスペインを支配してきたフランコ独裁体制を解体して、1978年憲法と呼ばれる主権在民の新憲法を成立させ、スペインを民主主義国家に変えて行くことに力を尽くします。
当時の週刊誌が、「スアレスのハラキリ」というタイトルで、サムライの格好をしたスアレス首相が、自らの出身基盤であるフランコ体制を次々に解体して行く姿を漫画化した挿絵入りの特集記事を載せたことがありました。スアレス首相の勇気には賞賛を送る一方で、長年わがもの顔にスペインを支配してきた独裁体制の終焉をちくりと皮肉る調子の記事でした。そしてそれは当時の庶民の気持ちをうまく言い表したものだったと思います。
スペイン人は当時を振り返って、「あの民主化への移行は本当にうまく運んだ」と口をそろえて言います。それは「もう内乱はコリゴリだ」という気持ちが国民のあいだで過激な言動を抑える作用を果たした一方で、保守的な体質の軍部を過度に刺激しないよう、当時の政治家たちが現実的な妥協を重ねながら慎重にフランコ体制の解体を図った結果でもありました。
(特赦法が生まれた背景)
スアレス首相は保守派の根強い反対を押し切って、1977年4月には共産党の合法化を行い、そして6月に実施された総選挙で第一党の地位を固めると、新憲法制定に向けて与野党の歩み寄りを推し進めます。そして、新憲法を保守派に呑ませるための妥協策のひとつとして「特赦法」が生まれた、という風に私は理解します。
特赦法の狙いは、ひとことで言ってしまえば、「この法律が成立する以前に軍人が犯した反乱の罪ならびに官憲が犯した人権侵害の罪を問わない」ということです。
従って、たとえ1978年12月に施行された新憲法で人権尊重を謳っていても、内戦の犠牲者が過去に遡って人権侵害による被害を訴える法律的な基盤がなくなってしまうということでした。
それは内戦中にフランコ軍の占領地で起こった暴行や殺戮の犠牲になった人たち、或いは官憲による不当逮捕・拷問を経験した人たち、そしてその家族にとっては、耐え難い妥協だったことでしょう。ヘミングウェーの「誰がために鐘は鳴る」の女主人公マリアのように、父親が共和派の政治家であったというだけの理由で、両親はフランコ軍に銃殺され本人は頭を剃られて暴行されたというような話しは、ヘミングウェーの小説の上だけのこととも言い切れないようです。
しかし今でも殆どのスペイン人が「民主化実現のためには、あの特赦法は止むをえなかったのだ」と言います。そして、内戦の記憶がひとりひとりのスペイン人の心の奥深いところで封印される一方、国民の合意という形で1977年の「特赦法」によって、政治的にも内戦の記憶が封印されてしまったのでした。
その特赦法から30年が過ぎ、そして内戦から70年が過ぎた2007年になって、やっと「歴史の記憶に関する法律」が生まれました。そしてこの法律によって、内戦とフランコ独裁の犠牲者に対して、国として人権侵害の事実があったことを公に認め、多分に象徴的な意味合いが濃いとはいえ、何らかの救済措置を講じる姿勢を明確に示したことで、遅まきながら犠牲者の名誉回復を図る動きが正式に認知されたということでしょう。
スペイン内戦の歴史を辿っていると、「戦争の記憶を一度は封印しても、いつかはそれに向き合わねばねらない時が来る」ということを痛感します。そして「戦乱の犠牲者は復讐を求めるべきではない。ふたつに分かれてお互いに殺しあった国民が、和解に達するのがいちばん大事なことなのだ」と自らが内戦の犠牲者でもある詩人マルコス・アナが静かに語るとき、私にはそれがスペイン内戦の歴史を越えて現代に通ずる呼びかけだ、という風に響くわけです。