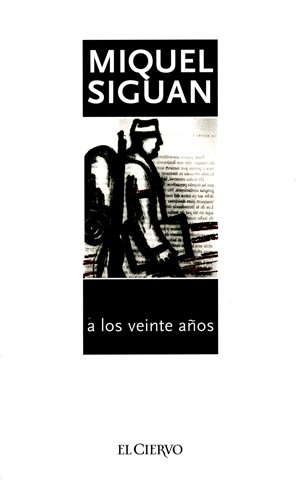1939年4月1日にフランコ将軍が内戦勝利宣言をして、足掛け3年に及ぶスペイン内戦が終わってから、今年でちょうど70年。ということで、スペインではこのところ内戦終結70周年にちなむテレビ番組や展示会、或いは新聞雑誌の特集記事を含め内戦をテーマにした出版物がずいぶん目に付きます。
その中でも特に目を引くのは、1939年1月末から2月初めにかけて、50万人近いスペイン人がフランコ軍の追求を逃れ一斉にフランス国境に押し寄せた、いわゆる「亡命スペイン人」の話題です。
1939年の年が明けた時点で、バルセロナに向け破竹の勢いで押し寄せるフランコ軍を押しとどめる力はもう共和国軍にはなく、兵士はもとより指揮官の中にも脱走する者が出る始末。共和国軍は徐々に崩壊しつつあるというのが実態でした。
一方バルセロナ市民のあいだでも、食料その他の生活必需品の欠乏が日増しに深刻になり、そのうえたび重なる空襲が続いたこともあり、厭戦気分が広がっている状態でした。そんな状況では、共和国側にまともなバルセロナ市の防衛戦を組織できるはずもなく、共和国政府はバルセロナからフランス国境に近いフィゲラスの町に移転を始めます。そしてフランコ軍は、ほとんど戦闘らしいものもなしに1939年1月26日にバルセロナ市を制圧しました。
内戦が始まって以来、フランコ軍が占領した地域では、共和派の軍人や政治家は勿論のこと、共和派の支持者と見なされるだけで、一般市民も逮捕されたり処刑されたりする例がひんぱんに起きたため、フランコ軍による攻撃が迫ってきた1月下旬ころから、バルセロナではフランスに逃れようとする共和派の人たちの動きが雪崩を打ったように始まりました。
50万人近い亡命者と言えば、全員が手を繋げば東京から大阪にまで届いてしまうほどの人数です。フランスに向け避難しようとする人たちを満載した車やトラックや馬車や、そして中には子供の手を引いて歩く人たちで、バルセロナからフランス国境までの約150キロの道路は大混乱の状態に陥ります。
戦局の成り行きを見れば、大量の共和派の避難民が発生するだろうことは、ある時点で充分予想された筈ですが、共和国政府の対応は後手に回りました。
実際に膨大な数の避難民が受け皿もないままフランス国境に向け動き始めたのを見て、共和国政府は急遽フランス政府に対し15万人の亡命者受け入れを要請しますが、フランス政府は最初この要請を拒否しました。しかし人道上の問題だという内外の批判もあり、1月28日に非戦闘員のみを対象に入国を認めます。
ついで2月5日には武器を持たないという条件で、共和国軍兵士の入国が許可されました。しかし2月10日にはフランコ軍が国境に達したため、フランス政府は再び国境を閉じてしまいます。わずか二週間たらずの間に、20万人を越える共和国軍の兵士と20数万人の市民がピレネー山脈を越え、大混乱のうちにとにかくフランスに入国したわけです。
もともとスペイン国境に近い南フランスの町は、人口数百人、数千人という小さな町がほとんどで、住民も保守的な人たちの多い地域です。そこへ前触れもなく一挙に何万人単位の避難民が押し寄せたのですから、フランス側の受け入れ態勢が整わなかったのは仕方のないことです。
しかし問題は当時のフランスの世論が、スペイン共和国政府に対して好意的でなかったことでした。それに加えてフランコ側は、共和派のスペイン人は革命をめざすアカであり、教会を焼き僧職者を殺戮した犯罪者である、というキャンペーンを張りました。もともと保守的な南フランスの小さな町々の住民が、共和派の亡命者たちを望まざる不法入国者として冷たい目で見たのには、こんな背景がありました。
子供の手を引き、命からがらピレネー山脈を越えて来たスペイン人の―家が、通りかかった家で一杯の水を頼んだら冷たく断られた、という類の証言には事欠きません。そしてほとんどの亡命者は急ごしらえの強制収容所に送り込まれました。
なかでも悪名高いのはアルジュレス・シュール・メール(Argeles sur mer)の収容所です。フランス政府は砂浜に鉄条網を張り巡らせただけで全く何もない浜辺に、何万人というスペイン人の亡命者を、まるで家畜でも扱うように囲いこんだのでした。
70年前にカタルーニャ地方からピレネー山脈越えでスペインの亡命者たちがフランスに入ったルートには、主なものだけで三つありました。私は今年の三月にそのルートのひとつで、スペインのポール・ボウ(Portbou)の町からフランス側の国境の町セルベール(Cerbere)へ抜ける、地中海岸沿いのスペイン亡命者たちの足跡を辿り、その北にあるアルジュレス・シュール・メールの収容所跡を訪ねてみました。
,+C%2B10,+Sa%2B15.jpg) Town of Portbou(Click on the photo to enlarge)
Town of Portbou(Click on the photo to enlarge)ポール・ボウはスペイン国鉄の終着駅で、トンネルを抜けるともうフランスです。最近の国際列車は軌道の巾を国境の駅でレールに合わせて調整できるようですが、スペイン国鉄は広軌でフランス国鉄とは線路巾が異なるため、昔はパリ発スペイン行きの夜行列車はポール・ボウ駅が終点で、そのあとバルセロナまで行くには、スペイン国鉄に乗り換えたものでした。
ポール・ボウは冬は突風の吹き荒れることが多い町で、むかし一度訪ねたことがありますが、その時はよく晴れた日だったにもかかわらず沖には三角波が立ち、山肌にへばりつくようにつけられた道路を歩くと、海からの突風で吹き飛ばされそうになったのをよく覚えています。ロバート・キャパの有名な作品のひとつに、冬のピレネー越えをする子供づれの亡命者一家の写真があります。
このポール・ボウの国境越えのルートは、スペイン内戦中の最大の激戦地だったエブロ川の戦いで活躍し、いちばんむずかしい撤退のしんがり役をつとめた、タグエーニャ第15軍団長の率いる部隊が辿ったルートでもあります。その共和国軍最後の部隊が国境を越える場面を、私はむかしロバート・キャパの自伝的小説「ちょっとピンボケ」の中で読んだ記憶があります。
それはこんな内容でした。「共和国軍の精鋭部隊がピカピカに磨き上げた銃を肩に、白馬に跨った共和国軍のモデスト将軍の前を右の拳をあげて敬礼しながら行進する。そして涙をこらえ「また戻って参ります」と叫びながら、次々に国境線を胸を張って越えて行く。フランス国境警備隊は驚き、一斉に捧げ銃の姿勢でこれを迎えた」、ということになっていました。
タグエーニャ司令官の回想録を読むと、兵士たちは連日の戦闘と長い行軍で疲労困憊していたようだし、モデスト将軍(当時は大佐)が白馬に乗っていたのどうか、フランス国境警備隊が本当に捧げ銃をしたのか、などはどうもはっきりしませんが、きっとキャパの目には、そうであって欲しいスペイン共和国人民軍の凛々しい姿が二重写しになっていたのでしょう。
 Memorial of 100,000 Spanish exiles
Memorial of 100,000 Spanish exilesフランスとの国境にはスペイン亡命者の記念碑が建てられています。碑文の趣旨は、「10万人のスペイン共和国の市民が三年間のフランコに対する戦いの後、1939年2月にこの道を辿って亡命の途についた。彼らはヨーロッパにおける反ファシズムの戦いの先駆者であった」という内容です。
ただし70年前にこの人たちが国境を越えたときのフランス政府の対応は、まるで共和派のスペイン人は未開発国からの不法入国者であるかのような扱いだった、というのが大方の意見です。
バルセロナの女流作家テレサ・パミエスは当時19歳で、共産党系のカタルーニャ統一社会主義青年連盟の指導者の一人でしたが、国境を越えた時の思い出をこんな風に語っています。「オーバーの上に白衣を着込んだ何人かの男たちが、私たちを家畜運送用の貨車に押し込む前にいろいろ質問をする。シラミはいないか、疥癬を病んでいないか、喀血していないか、性病に罹ってはいないか、金製品を持っていないか、フランスの通貨は持っているか、そして私たち娘に対しては、処女かどうかと尋ねる。フランス語のできるヌリは通訳しながら泣いていた」
 Vineyard on the hill
Vineyard on the hillフランス国境の町Cerbereを過ぎて地中海岸沿いに北上して行くと、小高い丘の急斜面は見渡すばかりのぶどう畑が続きます。いつか南スペインのハエン地方で目にした、山の急斜面を埋め尽くしたオリーブ畑を思わせる風景です。ガルナッチャ種のぶどうを主体にした糖度の高いワインの産地で、私たちも試飲してみましたが、ちょっとロゼを甘くしたような口当たりのよいワインでした。
 Tomb of Antonio Machado
Tomb of Antonio Machadoスペイン国境から北に15キロぐらい海岸沿いに走ると、コリウール(Collioure)の町に着きます。スペイン人の間では、この町は詩人のアントニオ・マチャードのお墓がある場所として知られています。
アントニオ・マチャード(1875-1939)は、今も幅広い愛読者を持つスペインの詩人ですが、 内戦の時には共和国政府支持の立場を鮮明にして、バルセロナ陥落の直前までスペインに踏み止まります。そして1939年1月末、病弱の母親と共にバルセロナからポール・ボウ経由で国境越えをしてコリウールの町にたどり着き、淋しくホテル住まいをしていましたが、一ヵ月後の2月末に失意のうちに亡くなっています。
町の墓地を入るとすぐ目に付く場所にマチャードのお墓があり、いつも誰かが花を手向けているようです。最近になってスペインでは、「マチャードはスペインの誇る国民詩人であり、従ってそのお墓はスペインに移すべきだ」、と主張する人が出てきました。
またコリウールの町がマチャードのお墓を観光資源に利用している、というたぐいの議論も耳にしますが、実際に現地を訪ねてみると、コリウールの町にはマチャードのお墓のありかを示す標識も見当たらず、通行人に何度も道を尋ねながら、やっと墓地にたどりつけたようなしだいで、「マチャードを観光に利用云々」の批判は、的外れだと思います。
 Argeles sur mer - a concentration camp for the Spanish exiles was maintained on this beach during 1939 to mid 4o's
Argeles sur mer - a concentration camp for the Spanish exiles was maintained on this beach during 1939 to mid 4o'sコリウールの町からさらに5キロくらい北に進むと、アルジュレス・シュール・メールに着きます。長く何キロにもわたって美しい砂浜が続く海辺の町です。夏は海水浴客で賑わうようですが、70年前にはたぶん地中海岸沿いの寒村のひとつだったのでしょう。
「やっと自由の国フランスに逃れることが出来た」とほっとしたスペインの亡命者たちを待っていたのは、このアルジュレス・シュール・メールの強制収容所でした。
それは収容所とは名ばかりで、最初は全く何もない砂浜をただ鉄条網で長方形に囲っただけでのもので、2月の真冬の時期に身を切るような海からの冷たい風に吹きさらされながら、毛布もなにもない人たちが砂浜を掘り、その穴に身を横たえて寒さをしのぶ「収容所」でした。
もちろん最初はトイレも水もなく、やがて少しずつバラック小屋が建てられますが、衛生状態が悪く赤痢が蔓延したりしたそうです。どういうわけかフランス赤十字は介入せず、わずかに米国と英国のクエーカー教徒が主として子供たちを中心に援助の手を差し伸べたたのと、スイスの国際赤十字からの救援があったのみ。
収容されたスペイン人たちは、寒さと空腹もさることながら、犯罪者なみに扱われ人間としての尊厳を傷つけられたことが、何といっても耐えがたかったと言います。
 Old photo of the concentration camp
Old photo of the concentration camp今回案内してくれたのは、バルセロナ郊外に住むA夫妻でしたが、A夫人の叔父様に当たる方は、内戦の末期に17歳で共和国軍に加わり、そのあと亡命者の一人としてこの収容所で過ごしたようです。
私たちが現地を訪ねたのは3月末のよく晴れた日でしたが、それでもカメラのシャッターを押す手がかじかんでしまうほどの冷たい風が、海から吹きつけていました。
A夫人の叔父様は、経緯はよく分りませんが、最後はナチスがオーストリアに設けたマウトハウゼン(Mauthausen)の強制収容所送りとなり、そこで若い生涯を閉じたということです。そう語りながら、いろんな思いが一挙にこみ上げてきたのでしょう、A夫人はそっと涙を拭っていました。
南フランスには、10箇所を越えるスペインからの亡命者を収容する施設がもうけられましたが、収容所生活を経験した人たちの証言を読むと「スペイン人亡命者は犯罪人扱いされた。フランス政府はスペイン人が長逗留しないようわざと酷い待遇をしたのだ。自由・平等・博愛という言葉はフランス人の間だけのことで、スペイン人には適用されなかった」などの発言が目に付きます。
そんな収容所生活から逃れるため、フランス政府が組織した外国人労働者中隊(CTE)に加わり、フランス軍の陣地構築や弾薬製造工場など危険な作業に従事した元共和国軍兵士の数は、何万人にも上りました。
またフランス外人部隊に志願した人、1940年6月にフランスがドイツ占領下におかれてからは、フランスのレジスタンス運動に参加した元兵士もいました。このうち、数千人の元共和国軍兵士が第二次大戦中に戦死し、さらに数千人がドイツ軍の捕虜としてナチスの強制収容所に送られ死亡しています。
共和派の人たちの中には、もし欧州でファシズムに対する戦争が始まれば、他国に先駆けファシズムと戦っている共和国政府に対し世界の支援が集まるはずだ。それまではフランコとの戦争を戦い抜くべきだ、と考えた人は少なくありませんでした。皮肉なことに内戦に敗れたスペイン共和国の兵士たちは、亡命先のフランスで第二次世界大戦に巻き込まれ、再びファシストとの戦いに命をかけることになったわけです。
亡命者の中には、運良くメキシコはじめラテンアメリカ諸国に移民として受け入れて貰った人たちもいました。その数は2万人前後ではないかと推定されます。これらのラテンアメリカに移住したスペイン亡命者については、また稿を改めて述べようと思っています。
40数万人の亡命者のうち大半が南フランスの強制収容所での生活に絶望し、再び内戦後のスペインに戻ります。しかし帰国と同時にフランコ政府の手で逮捕され、入獄あるいは処刑されるという厳しい処分を受けた人たちが多数にのぼりました。そしてぶじに生き延びた人たちも、その後のフランコ体制下の30数年間を、肩身の狭い思いで暮らすことになります。
 Memorial of Spanish Republicans interned in the concentration camp
Memorial of Spanish Republicans interned in the concentration camp砂浜の片隅に、強制収容所があったことを示す看板と記念の石碑が建っています。アルジュレスの町の人たちにとって、いや或いはフランス人にとって、この強制収容所の歴史は忘れ去ってしまいたい記憶のひとつではないかと思います。私たちが石碑を見つめている間に、何人もの人が犬を連れて通り過ぎましたが、誰ひとり立ち止まることはありませんでした。ましてや夏の海水浴客に至ってはなおさらのことでしょう。
歴史上のできごとのうち、歴史を書く人や読む人にとって都合の悪い内容は、とかく忘れ去られたり無視されたりするものです。
しかし、この美しい砂浜にむかし強制収容所があったこと、そしてフランスはファシズムと戦ったスペインの亡命者たちを、この強制収容所に閉じ込めたという事実を石に刻み、その記憶を石碑の形でいつまでも残しておくべきだと考える人たちが、たとえ少数とは言え存在することに、私は歴史にちゃんと向かい合おうとするフランス人の姿勢を見る思いがします。