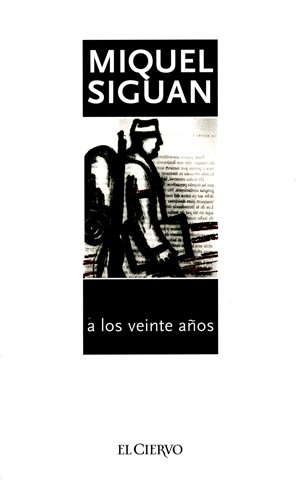(このテルエル県の略図をクリックすると画像が拡大されます)

(モラ駅周辺)
スペイン内戦の回想録「二十歳の戦争」の著者ミケル・シグアン(Miquel Siguan)氏は、1938年1月に100人ばかりの若い同期の召集兵と共にバルセローナ市近郊の訓練基地を出発し、列車でテルエル戦線に到着した時の印象をこう述べています。
「今朝目が覚めたとき、列車の窓から見た光景にぼくは驚いた。何度も目をこすったぐらいだ。この汽車の旅では、ずいぶん変化に富んだ風景を次々と見てきたが、これまで目にしたのはどれも耕作地であり、人が住んでいる土地だった。ところが、いま目の前に広がっているのは無人の荒野だ。木も草もなければ、人間がいるという気配がまったく感じられない荒野である。ただのっぺりした平原が、これまた同じように一木一草も見当たらない裸の丘に囲まれているだけなのだ。」

(モラ駅舎)
「線路脇にかなり痛んだレンガ造りの建物があり、村の姿はどこにも見当たらないものの、残っている標識からそれがモラ村の駅らしい。近くを一本の道路が走っているが、それはまったく人気のない平原を一直線に延び、水平線のかなたに消えている。列車とぼくらだけが、このあたりで唯一の生命のしるしというわけだ。」 ………………………………………………………………………………………………
「人里離れた駅のプラットフォームに一団となって集まったぼくらは、まるでわずかばかりの身の回り品を抱えた移民の群れのようだ。」 (第一章「到着」)
テルエルの戦いから70年が過ぎた今年の春、私は「二十歳の戦争」の舞台となったテルエル県を訪ねてみました。この70年の間に開発が進み植林などが行われたということもあるのでしょうが、現地を見たかぎりではモラ駅周辺はたしかに依然として人気のないさびれた場所ではありますが、「木も草もなければ、人間がいるという気配がまったく感じられない荒野である」という回想録の記述とは少し違うな、という印象でした。
或いはこの部分は、家族にもそして緑あふれる故郷のバルセローナにも別れを告げ、激しい戦いが続く冬のテルエル戦線に着いた時の、当時19歳だった著者の心象風景と理解すべきなのかも知れません。
モラ駅、正確にはモラ・デ・ルビエロス(Mora de Rubielos)駅は、町まで15キロ近くも離れている無人駅で、今でも駅の周りには2-3軒の家があるだけで、一日に何本かの列車が発着する時は別なのでしょうが、ふだんは本当に人影もなく、一匹の犬の姿すら見かけない、まことにさびれた雰囲気でした。

(Mora de Rubielos)
モラ・デ・ルビエロス町は、テルエル市から40キロくらいの距離にあり、人口は1,600人でテルエル県東部地方では大きな町です。モラ町のみどころと言えば、14世紀から15世紀にかけて築かれた城壁の一部が残っているのと、同じ頃に町の中心部に建てられたモラ城やゴチック様式の聖マリア教会などが有名です。私たちは数時間滞在して、教会のすぐ前のレストランでコーヒーを飲んだだけでしたが、モラ町はこじんまりとして落ち着いた雰囲気を今も保つ、なかなか味のある町でした。

(Rubielos de Mora - Patio of the City Hall)
モラ町から10キロぐらい東に、ルビエロス・デ・モラ町(Rubielos de Mora)があります。名前が似ていてまぎらわしいのですが、ルビエロス町は人口700人ぐらいの小規模な町ながら、15世紀から16世紀にかけて築かれた城壁や古い建物や教会などがよく保存されていて、石畳の通りを散歩するのがとても楽しい町です。
ルビエロス町は、シグアン氏たち召集兵がモラ駅に到着したあと、迎えのトラックに座ることもできないほどのすし詰めの状態になり配属先の部隊を探してひと晩中あちらこちらと移動したあげく、やっとのことで明け方に町に着き、前線で初めての仮眠をとった場所でもありました。
「日の出も間近になったころ、やっとトラックが停まる。今度ばかりはほんとうに石畳の広場で停まった。トラックを降りる、というよりむしろ全員で転げ落ちる。そして落ちたところでそのままぼくらは横になって眠り込んでしまった。
二十歳の身体というのは、まるでゴムみたいに柔軟で、数時間の睡眠で疲れがすっかりとれてしまう。ぼくらが呼び起こされたときには、もう正午を過ぎていた。」
……………………………………………………………………………………………
「ぼくらが自分でいろいろ調べた結果、ここはルビエロス・デ・モラという古い大きな村で、なかなか豪壮で立派な建物もある。村の通りをぶらぶら歩いていたとき、意外なものに出くわした。戸締り厳重な修道院らしい建物から、男声合唱が聞こえてきたのである。それはどんな歌詞にでも合いそうな鼻歌のように「もしも手紙を寄越すなら おれの居場所はご承知だ テルエル占領したあとは ルビエロスで牢屋入り」と歌っている。一緒に歩いていた仲間たちもぼくと同じくらいびっくりしてしまい、いったいこれはどう説明すればいいのだと、いろいろ想像を巡らせる。でも、彼らは他に用事があるからと、ぼくを置き去りにして行ってしまった。彼らの用とは、ルビエロス村の娘たちは見かけ通り素っ気ないのか、この村には開いている居酒屋は一軒もないのか、確かめたいということなのだ。そんなわけで、ぼくは歌声の漏れてくる窓のそばにひとり残って、その歌についてあれこれと考えてみる。この歌についてはこれからも繰り返し考えることになるのだろう。」 (第一章「到着」)

(第84旅団の宿舎として使われたカルメル会の修道院、The old convent of the Carmelitas Calzados)
悲劇の第84旅団
シグアン氏がルビエロス町で修道院の窓越しに漏れ聞いた歌声の主というのは、前線復帰の師団長命令に不服従を唱えたため「反乱」の罪に問われ、修道院で身柄を拘束されていた第84旅団所属の兵士たちでした。この声の主がその後どうなったのかは分りませんが、この事件で下士官を含む46名の兵士が、裁判を経ることもなく師団長の即決で銃殺刑に処せられています。
1938年1月に第40師団のテルエル市内掃討作戦の先頭に立った第84旅団は、アナキスト民兵部隊を母体に編制された旅団で、2,000人くらいの兵力でした。当時共和国軍を支配していた共産党からは、規律面で問題が多いなどと何かにつけて批判のやりだまに上げられていたアナキスト部隊ですが、そのアナキストが母体の3個旅団(第82旅団、第84旅団、第87旅団)で第40師団が編制された時、国境警備隊の出身者で、メリダ市長を勤めた経験を持つニエト中佐が、新しい師団に共和国軍の規律を徹底させるという責任を担って第40師団長に就任しました。
1937年12月半ばに始まったテルエル市の攻防をめぐる戦いは、1938年1月8日のフランコ軍守備隊の降伏でひとまず共和国側の勝利となりましたが、勝った共和国軍も、例年にない厳しい寒さと雪に苦しみ、兵力の2割から3割を消耗するほどの激しい戦いが一ヶ月近くも続いたため、どの部隊も兵士の大半が病気や疲労で体力の限界に達していたというのが実情でした。中でも第84旅団の場合は、テルエル市内の掃討作戦を指揮した少佐が、テルエル占領に成功すれば長い休暇が与えられ、おまけに報奨金の支給や昇進もある筈だなどと、常識では考えられないやり方で士気を鼓舞したため、兵士たちは基地に戻り休息できる日を夢見て激しい戦いの日々に耐えていました。そして第84旅団の兵士たちに予備軍として一時休養、という待ちに待った命令が伝えられたのは1月半ばのことでしたが、ちょうどまさにその時フランコ軍によるテルエル奪回の猛反撃が始まり、各地で共和国軍の防衛線が破られ始めたため、すでに休養中の各部隊に対しても即時戦線復帰の命令が出されるという事態になっていた時でした。
特に84旅団の機関銃中隊など一部の部隊は、重い機関銃や弾薬を担ぎ、テルエル市近郊の塹壕から傷む足を引き摺りながら歩き続け、やっと一日がかりでルビエロス町の基地にたどり着いた途端、また即時戦線復帰の師団長命令が出たということで、それまでに溜まりに溜まっていた不満が一挙に爆発し、約束が違うとして戦線復帰命令を拒否する動きが起こりました。
ニエト師団長は、第84旅団の兵士たちが宿舎にしていたルビエロス市内の修道院に出向き、前線復帰を拒否する者には交代を派遣するので、武器を上官に預けた上そのむね申し出るよう命じました。実際に不服従を具体的な行動で示したのは旅団員の一割にも満たない200人足らずの兵士だったようですが、その全員が武器を棄てた途端に逮捕監禁され、そのうち下士官を含む46人については裁判なしの即決で銃殺が決まりました。そしてこの46人は、翌朝まだ夜が明けぬうちに理由も告げられずルビエロスの町外れに連行され、トラックから降りたところを機関銃の一斉射撃で銃殺されるという、まるでだまし討ちのような処刑が行われました。
1月8日のテルエル市占領までは、テルエル攻撃の尖兵としてロバート・キャパのカメラにおさまったりして英雄扱いだった第84旅団の兵士たちですが、わずかその10日後に一部の兵士は師団長から「反乱者」の烙印をおされて銃殺され、銃殺刑を免れた者も懲罰部隊送りの処分となりました。そして第84旅団は解隊と決まり、兵士たちはそれぞれいくつかの部隊に分散して配属され、テルエル占領の栄光に輝く第84旅団は消滅してしまいました。
「反乱者」とされたのは、その大半が文字も読めない農民で、内戦が始まると義勇兵としてバレンシアのアナキスト民兵部隊に加わり、ファシストと戦うことに命をかけた勇敢な兵士たちでした。しかし内戦開始から一年が過ぎ、共和国軍が組織化され義勇兵にも軍法が適用される事態になってもその意味がよく理解できなかったようで、師団長命令を拒否した時も、いまだにアナキスト部隊の伝統を信じて、兵士と部隊指揮官とはお互いに苦楽を分かち合う仲間であり、非人間的な命令を拒否しても上官は理解してくれる筈だ、などと思い込んでいた兵士もあったようです。そして上官の命令を拒否することが軍隊では死罪に値する可能性がある、などというのはたぶん彼らにとっては思いもよらないことだったのでしょう。そんな雰囲気の中でも、雲行きが怪しいと感じ混乱に乗じて逃亡した兵士や、過酷な処罰を予期して親しい部下に密かに逃亡を勧めた部隊長などもあったため、そのおかげで命拾いをした兵士がいたということです。
なぜニエト師団長が兵士たちの前線復帰命令拒否に対して常識はずれの過酷な処分で臨んだのか、それを理解するうえで重要だと思われる点がいくつかあります。
そのひとつは1938年1月1日付けの中央参謀本部長より各部隊長宛ての命令で、部隊の士気低下を招く言動に及ぶ者は銃殺を含む厳罰をもって対処するよう指示があったことです。ニエト師団長はこの指令に従い、命令不服従者には銃殺刑をもって対処すべきだと考えた可能性があります。
もうひとつは共和国軍の権力の中枢にいたのは共産党員が多かったということです。ちょうど同じ時期に、第11師団長が部隊員の消耗を理由に第22軍団長の前線復帰命令を拒否したのですが、それが共産党の英雄リステル第11師団長であったため、命令拒否を咎められることもなく、逆に軍団長がその命令を撤回するという結果になりました。おまけにその後リステル師団長はテルエル攻略の戦功で、民兵出身者としては初めての中佐昇進を果たしています。共産党員に対するえこひいきではないか、という批判が出るゆえんです。また共産党が権力を握る共和国軍では、アナキスト部隊はなにかと批判の対象になり易かったという背景もありました。ちなみにニエト第40師団長は社会党員でした。
そしてもう一つは、テルエル市内の掃討作戦の遅れなどで、軍上層部の間でニエト師団長の指揮ぶりにとかくの批判があったことです。従って師団長としては、命令不服従問題でさらに指揮官としての自分の名声に傷がつくことを懸念していたに違いありません。それと師団長は師団付き政治コミサール(政治委員)の意見を聞いてこの問題に対処したようですが、第40師団の政治コミサールは19歳の共産党員で、銃殺刑になった軍曹など下士官を含む46名の兵士を処刑対象者として選んだのもこの政治コミサールだったと言われます。19歳の若さで師団付き政治コミサールになるというのは、よほど本人が有能であると同時に共産党首脳との人脈にも恵まれたエリートだったからでしょう。政治コミサールはその報告書などを通じて部隊指揮官の言動を軍首脳に伝える役目も果たしますから、ニエト師団長は共産党出身の政治コミサールの目を意識せざるを得ない立場にありました。それやこれやで、師団長が第84旅団の兵士たちに対して厳しい態度で臨む姿勢を強調せざるを得ない状況にあったことは確かです。
しかし重さ50キロを越える鉄の固まりのような機関銃を担ぎ疲労困憊して基地に戻ったばかりの兵士たちが、指揮官に約束された長期休暇が反故になったたと憤っている時に、前線復帰命令に従わないからと裁判手続きも経ず即座に銃殺刑に処すべきだと判断したこと、しかも純朴な農民出身の兵士たちをだますようなやり方で身柄を拘束のうえ銃殺した、というような事情を勘案すると、ニエト師団長及びそれを補佐した政治コミサールの見識には疑問を感じざるを得ません。疲労困憊している部下のため、軍団長の前線復帰命令を拒否した第11師団長に比べて、余りにもその姿勢の違いが大きいことを痛感します。また命令拒否の事態に至ったのには、直属の部隊長が部下の兵士をよく掌握していなかったという問題もあるのでしょうが、はっきりしているのは銃殺などの厳しい処分を受けたのは兵士のみで、将校やそれを補佐すべき政治コミサールの責任がどう問われたのかはよく分りません。そしてニエト師団長もこのあと10ヶ月くらいで大佐に昇進しています。
この事件に関する公式な記録としては、第40師団長からレバンテ方面軍司令官に宛てた三頁の報告が残っているだけで、本来なら詳細な記録を残すべき師団付き政治コミサールなどの報告には、本事件の顛末に関する記載は見当たらないようです。実態に照らして過酷過ぎると思われる師団長の処分について、共和国軍首脳は公の記録として残すことを避けたかったのかも知れません。そんなこともあって、この事件は長いあいだ闇に葬られたままになっていましたが、最近になり少しずつその詳細が一般の目に触れるようになりました。

(ルビエロスの城壁)
ルビエロス町は城壁に囲まれ、石畳の通りを通行人と車が共有している古い町です。わずか人口700人くらいの規模の小さな町なのに、古い建物を修復しながらいい雰囲気の街づくりをしているな、と感心させられました










,+Level(0.96),+Sa%2B15.jpg)
.jpg)
,+Level,+C%2B5,+Sa%2B20.jpg)
.jpg)

,+C%2B10,+a%2B20,+Level+.jpg)
,+C%2B14,+Sa%2B30,+Level(1.10).jpg)


,+C%2B5,+Sa%2B10,+Level(mid).jpg)